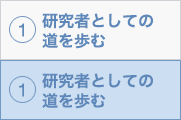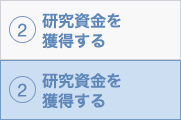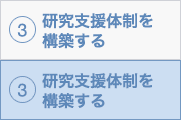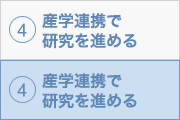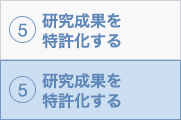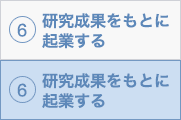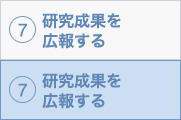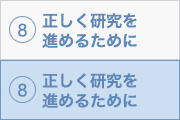組織、そしてアカデミアの中に、
自分の立ち位置を確立する
山形大学医学部 テニュアトラック助教
田中 敦氏
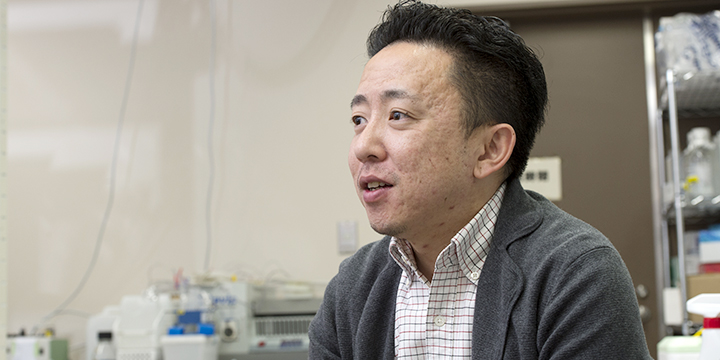
PI(Principle Investigator)となり、自らが運営するラボを持つ。研究者として、アカデミアの中で生きていこうと決意した人であれば、キャリアパスのひとつの目標となるだろう。山形大学のテニュアトラックプログラムに採用され、PIとなるチャレンジの途上にいる田中敦氏に、これまでの経験と現在直面する課題、そして将来像についてうかがった。
・「組織に所属すること」を意識し、組織の考えを知った上で応募、ラボ運営をする。
・人材や外部リソースも考慮に入れて予算を使い、考えるための時間を確保する。
・自分オリジナルの研究テーマを確立し、その魅力を伝えて人を巻き込む。
独立でありながら、組織に所属していることを意識する
 田中氏が独立を考えたのは2012年7月、助教として所属していた東京医科歯科大学の研究室が東京大学へ移籍することが決まったときだった。「スタッフの中で、独立できる人はこの機会に考えてほしい」。その教授の言葉をチャンスと捉え、つてのある研究者に空きポストを聞いたり、JREC-INで求人情報を探したりして、現在の所属を含めて複数に応募。最終的に、医学部の中で基礎研究を進める人材を求めていた現在の所属に採用されるに至った。
田中氏が独立を考えたのは2012年7月、助教として所属していた東京医科歯科大学の研究室が東京大学へ移籍することが決まったときだった。「スタッフの中で、独立できる人はこの機会に考えてほしい」。その教授の言葉をチャンスと捉え、つてのある研究者に空きポストを聞いたり、JREC-INで求人情報を探したりして、現在の所属を含めて複数に応募。最終的に、医学部の中で基礎研究を進める人材を求めていた現在の所属に採用されるに至った。
「組織の求めるものと、自分がやりたい研究とが合っていないと、いくら実績があっても採用はされないと思います。その意味で、ちょうどいいタイミングで、求めるポストと巡り会えたのは運がよかったですね」。PIは独立した研究者であるとはいえ、あくまで組織の中のメンバーである。大きな枠組としては研究の方向性、小さな点としては予算等の学内申請の時期やイベント実施時の段取りなど、「大学や部局のルールをきちんと知って、それに合わせてラボを運営する必要があります」。独立の気概を持ちつつ、組織内の人たちとのコミュニケーションを怠らないことが大切なのだ。またこのことは、求人に応募するときも同じだという。研究環境がどのようなものか、組織として向いている方向性はどこなのか、もしその組織内に知人がいるならば積極的にヒアリングして自分に合う場所を探すことが、採用されやすさにもつながるはずだ。
考える時間を確保できるよう、予算の使い道を決める
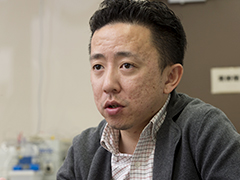 2013年2月、山形大学に着任した田中氏が行ったのは、何よりもまず研究できる環境を整えることだ。異動の前後2か月間は、東京医科歯科大学、東京大学、山形大学を回りながら、実験や会議を進めた。マウスの移動には書類手続きを含めて半年はかかるため、異動前にできるだけタンパク質等のサンプルを抽出しておき、山形大学に移ってから解析を進められるように準備した。「こちらに来て入った場所が遺伝子実験施設の中だったため、異動前からすでに実験台があり、共用機器を使って基本的な実験はできる体制があったのです。すぐに研究を再開できるかどうかは求職の際に重視した点で、山形大学に来る際の大きな決め手になりました」。
2013年2月、山形大学に着任した田中氏が行ったのは、何よりもまず研究できる環境を整えることだ。異動の前後2か月間は、東京医科歯科大学、東京大学、山形大学を回りながら、実験や会議を進めた。マウスの移動には書類手続きを含めて半年はかかるため、異動前にできるだけタンパク質等のサンプルを抽出しておき、山形大学に移ってから解析を進められるように準備した。「こちらに来て入った場所が遺伝子実験施設の中だったため、異動前からすでに実験台があり、共用機器を使って基本的な実験はできる体制があったのです。すぐに研究を再開できるかどうかは求職の際に重視した点で、山形大学に来る際の大きな決め手になりました」。
また、同じタイミングでテニュアトラック助教となった越智陽城氏と共同で、着任後すぐに事務補助員を雇い、事務処理関係を任せられる体制をつくった。「考えるのも手を動かすのも自分ひとりなので、できる限り研究に集中できる時間を確保したかったのです」。その後、学生をアルバイトに雇って実験を教え込み、ルーチンワークを任せられる体制を整えた。さらに、できるだけ受託サービスの利用や、共同研究先との連携などで研究を進めるようになったという。「2~3年で結果を出さないと、次がない。そのプレッシャーもあり、予算配分の考え方が大きく変わりましたね。自ら手を動かすことも大事ですが、任せられることは任せて、考えること、研究費の申請書を書くことにより多くの時間を使えるように心がけています」。
独立することとは、自らの立ち位置を確立しチームをつくること
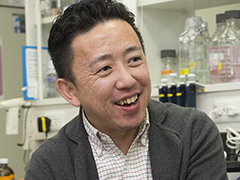 現在の研究テーマは、九州大学で博士号を取得後にポスドクとして米国立衛生研究所(National Institutes of Health ; NIH)に勤めていた頃から温めていたものだ。その後、医科歯科大の助教として、自分ではそろえることのできない恵まれた環境の中で先達の知恵に触れながら研究を進め、そこから巣立った。現在は、自らのコンセプトで研究費を申請し、独自の研究とともに共同研究を進めている。
現在の研究テーマは、九州大学で博士号を取得後にポスドクとして米国立衛生研究所(National Institutes of Health ; NIH)に勤めていた頃から温めていたものだ。その後、医科歯科大の助教として、自分ではそろえることのできない恵まれた環境の中で先達の知恵に触れながら研究を進め、そこから巣立った。現在は、自らのコンセプトで研究費を申請し、独自の研究とともに共同研究を進めている。
テニュアトラックを経て、今後テニュアを獲得したPIとして本当に独立するためのチャレンジを続ける田中氏は、今の立場を「責任とリスクを負い、代わりに自由を得た」と表現する。「今の目標は、自分のスタンスを確立することです。あの研究といえば田中だ、と言われるようになってから、今度は対等な立場でお世話になった教授たちと共同研究を行いたいですね」。
ただ、その挑戦は自分ひとりで行うものではなく、人を巻き込んでこそ、と田中氏は考えている。自分の研究への情熱を学生や研究員に伝え、「一緒にやりたい!」と思う人材を仲間に引き入れ、チームをつくる。それが大学の教員として、教育と研究の両方を担う意義なのだ。そのためにも積極的に授業を持ち、外部のセミナーや講義の機会にも応じるようにしている。山形から東京までは、片道3時間。その程度の距離なら、日帰りで飛び出していく。
独立のためのチャレンジは、予定通りに進むことばかりではない。それでも自分が打ち立てた研究のコンセプトを信じ、毎日方向修正をしながら走り続ける。その情熱を周囲に伝え、共に走る仲間を増やし、いつたどり着けるかわからないゴールに向かって研究を進めていく。ラボを立ち上げること、PIになることとは、自らが振る旗のもとに集うチームをつくることでもあるのだろう。
(取材・文 株式会社リバネス 2014年1月14日取材)
*コンテンツの内容は、あくまでも取材をうけた方のご意見です。