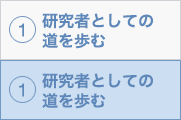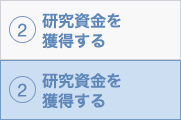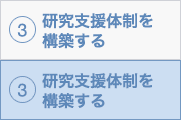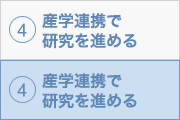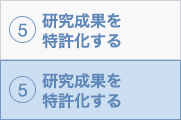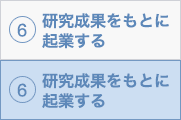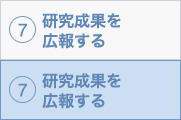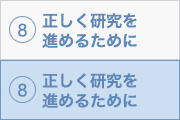戦略的な先行投資で研究プロジェクトを育てる
明治大学 研究活用知財本部長 / 農学部 教授
長嶋 比呂志氏

明治大学は、2005年に「明治大学研究・知財戦略機構」を立ち上げ、研究室単位の研究を、大きな研究プロジェクトへと発展させている。その機構の意義やシステムについて、長嶋比呂志氏にお話をうかがった。長嶋氏は同機構の研究活用知財本部長である一方、自身も機構のサポートを受けバイオリソース研究国際インスティテュートを主宰している。
・研究力を向上させるため、研究プロジェクトを育成する組織的枠組みを構築する。
・先行投資により実績をつくり、それをもってさらなる外部資金獲得へとつなげる。
・その研究組織を代表できるような研究を、組織内部から育てていく。
研究大学としての一面を構築する
 教育、研究、社会貢献が大学の使命の3本柱といわれるようになって久しい。長嶋氏は「明治大学は、東京に立地していて卒業生も多く、教育や社会貢献については一定の水準を保っていると思います。一方で、研究大学としてのステータスはどれくらい確立できているのかといえば、大学内部のスタッフにも、まだ足りないという認識がありました」と話す。明治大学の研究大学としての側面を強化し、研究力の向上を目指すための組織として、研究・知財戦略機構は発足した。①世界水準の研究を推進するため、重点領域を定めて研究拠点の形成を図ること、②研究の国際化を推進すること、③それらの成果を広く社会に還元することの3つの目的をもち、研究の企画立案段階から、生まれた成果を活用する段階まで、教員が行う研究を総括し、サポートしている。
教育、研究、社会貢献が大学の使命の3本柱といわれるようになって久しい。長嶋氏は「明治大学は、東京に立地していて卒業生も多く、教育や社会貢献については一定の水準を保っていると思います。一方で、研究大学としてのステータスはどれくらい確立できているのかといえば、大学内部のスタッフにも、まだ足りないという認識がありました」と話す。明治大学の研究大学としての側面を強化し、研究力の向上を目指すための組織として、研究・知財戦略機構は発足した。①世界水準の研究を推進するため、重点領域を定めて研究拠点の形成を図ること、②研究の国際化を推進すること、③それらの成果を広く社会に還元することの3つの目的をもち、研究の企画立案段階から、生まれた成果を活用する段階まで、教員が行う研究を総括し、サポートしている。
明治大学で行われている研究プロジェクトは、実績や規模の大きさによって、特定課題研究ユニット(以下、ユニット)、研究クラスター(以下、クラスター)、特別推進研究インスティテュート(以下、インスティテュート)とランクアップしていく仕組みになっている。教員が自分の研究プロジェクトを立ち上げたい場合、まずはユニットを組織し、機構に申請することから始まる。
研究プロジェクトを成熟させるための投資
 ユニットは、明治大学の専任教員が、5年以内と定められた期間内で学内外の研究者と共同研究を推進するものだ。申請された案件はすべてユニットとして受理され、組織づくりの面でサポートを受けることができる。「各ユニットで採用した研究員や研究支援人材は、機構の所属となります。こういった『ポスト』があるだけで、スタッフの雇用の手続きが大変容易になるのです」。研究に必要な資金は外部から得る必要があるが、その運用についても機構がサポートする。
ユニットは、明治大学の専任教員が、5年以内と定められた期間内で学内外の研究者と共同研究を推進するものだ。申請された案件はすべてユニットとして受理され、組織づくりの面でサポートを受けることができる。「各ユニットで採用した研究員や研究支援人材は、機構の所属となります。こういった『ポスト』があるだけで、スタッフの雇用の手続きが大変容易になるのです」。研究に必要な資金は外部から得る必要があるが、その運用についても機構がサポートする。
ユニットとして研究活動を行い、成果がある程度出てきたところで、次は研究クラスターへの昇格を狙うことになる。教員から提案された案件に対して審査が行われ、条件を満たしたものが採択される。クラスターでは、それほど大きな額ではないが大学から資金的支援を受けることができる。しかし「研究クラスターに応募するテーマは、科学研究費補助金(科研費)の基盤研究(S)または(A)相当の規模の研究費に毎年応募することが条件になっています」。応募してくるからには、それなりの実績と体制ができているはず、という想定のもと「大学からの支援をうまく使って科研費(S)や(A)を獲得できるようになってくださいね、というメッセージでもあるんです」。この資金的支援を、長嶋氏は「呼び水」と表現する。実際、ユニットの期間で成果を出し、体制も整えられた「成熟」したグループが応募してくるという。
大学の看板を背負える研究を内部から育てる
クラスターの審査では、ユニットとしての活動において外部資金をどれだけ獲得しているかという実績も問われるが、研究内容そのものが厳しく評価される公的資金とは異なる審査ポイントがある。それは「応募してきた教員がやろうとしていることが、『明治大学の一種の看板になり得るか』ということです」。明治大学の研究力を代表するようなプロジェクトになり得ると見なされた場合、研究テーマの流行り廃りとは関係なく採択されるチャンスがあるのだ。外部資金よりクラスターの方が採択されやすいとは一概にはいえないが、公的資金よりもフレキシビリティの高い制度であるといえる。
そして、クラスターが基盤となってさらに大きな外部資金を獲得できたときや、クラスターではないグループが大規模資金を獲得したとき、インスティテュートに昇格する。
 長嶋氏が代表研究者を務めるバイオリソース研究国際インスティテュートは、2009年にユニットからクラスターに昇格。2011年に、JST戦略的創造研究推進事業のERATOやCRESTの予算を獲得し、インスティテュートとなった。遺伝子改変ブタやクローンブタを用いて、生物・医学系の基礎研究を臨床応用に橋渡しをする「トランスレーショナルリサーチ」を標榜している。クラスターへの応募時、これまでの研究実績や連携している研究者のネットワークを整理するとともに「なぜ、農学部の教員が、医学部をもたない明治大学で臨床医学への応用を見据えた研究を行う必要があるのか」研究の意義をわかりやすくまとめ直した。それが「明治大学らしい」研究テーマへの先行投資であるクラスターに採択された大きな要因であることは想像に難くない。
長嶋氏が代表研究者を務めるバイオリソース研究国際インスティテュートは、2009年にユニットからクラスターに昇格。2011年に、JST戦略的創造研究推進事業のERATOやCRESTの予算を獲得し、インスティテュートとなった。遺伝子改変ブタやクローンブタを用いて、生物・医学系の基礎研究を臨床応用に橋渡しをする「トランスレーショナルリサーチ」を標榜している。クラスターへの応募時、これまでの研究実績や連携している研究者のネットワークを整理するとともに「なぜ、農学部の教員が、医学部をもたない明治大学で臨床医学への応用を見据えた研究を行う必要があるのか」研究の意義をわかりやすくまとめ直した。それが「明治大学らしい」研究テーマへの先行投資であるクラスターに採択された大きな要因であることは想像に難くない。
しかし「どんな研究が『明治大学らしい』か、実は私たちもよくわからないんですよ」と長嶋氏は話す。大学は、ユニットから大学の色を示せるようなものを戦略的に育てていく枠組みを構築しただけで、基本的には「研究者の自発性を支援する」ボトムアップ型のしくみになっている。「そのテーマがどれくらいホットなものなのか......、明治大学は人文系・社会科学系の研究も多く、一概に論文数やインパクトファクターといった尺度で測ることができないのです」。それでもやはり、学内で育ってきた研究への支援を手厚くすることによって大学の研究力を向上させたいという長嶋氏。今の明治大学においては、学内で自発的に立ち上がってきた研究を育てることそのものが、明治大学らしさであり、戦略のひとつなのだ。
(取材・文 株式会社リバネス 2014年2月3日取材)
*コンテンツの内容は、あくまでも取材をうけた方のご意見です。