企業
株式会社MiDATA
代表取締役社長
後藤 司 氏(右)
シニアマネージャー・シニアAIエンジニア
大川 幸男 氏 博士(理学)(左)

ChatGPTの公開を皮切りに、AI技術は爆発的に世界中に普及し始めています。一方で、未知数の技術ゆえに多くの企業がAIのポテンシャルを生かしきれていない状況も生まれています。株式会社MiDATAは、経験豊富なデータサイエンティストと高度専門教育を受けた専門人材が在籍するAI専業企業として、「Science that makes you smile:)」を経営理念に掲げ、人と科学をつなげるAI関連サービスを提供しています。

後藤 当社は株式会社リンクバルの子会社であり、同社のAI推進室を前身とするAI専業企業です。設立は2023年5月。AIソリューションの開発・提供やAI活用コンサルティングを主な事業領域としています。
大川が担当しているコンサルティングサービスでは、AIやデータ分析の専門性を有するエンジニアやコンサルタントを派遣して、お客様ごとに異なるお悩みを解決し、プロジェクトに伴走するサービスを提供しています。いわば「人が商品」と言えるサービスであり、高い専門性やノウハウを有していることはもちろん、お客様と寄り添う人間性も必要とされます。
大川 私の仕事は、社内では「売り物担当」とも呼ばれています。種々のお客様の課題解決に資する汎用的なソリューション(売り物)開発はもちろんのこと、お客様に派遣する専門人材(売り物)の育成も私の主要なロールです。最近関わった事例で印象的だったのは、デジタルマーケティング会社のレコメンドシステムの開発です。ECサイトが乱立して多種多様な商品が氾濫している今の時代に、ひとりのユーザーがサービスを利用したことで残すログは商品の数に対してとても少ないのです。ですから、ユーザーが示す興味の多寡にグラデーションをつけるために数理的にどうアプローチするか、またそれを実際に仕組みの上にどう載せるかを考えるのが大変でした。
ただ、「この課題にはどうアプローチしてどう解決しようか」と思考しているときにはアドレナリンが頭の中を駆け巡ってとても楽しいですし、お客様に対して意義のあるアウトプットを示せたときには、大きなやりがいを感じます。
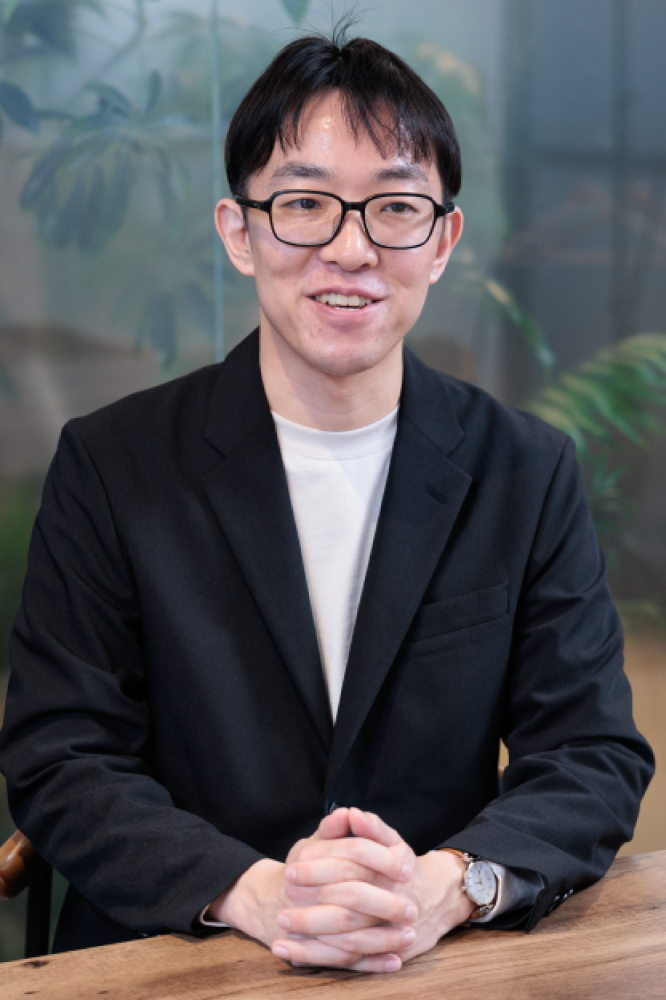
大川 私は、数論幾何学という分野で整数論的な幾何学を研究していました。基礎的な学習を済ませた後、修士、博士とその研究を続けて、海外の専門誌に3本の論文の掲載経験があります。その後、ポスドクとして1年半ほどの大学勤務を経て、企業に就職しました。
研究者としてアカデミアに残る選択肢もあったのですが、ポスドクで2年契約の1年目が終了した頃に、企業への就職を考えるようになりました。当時は20代最後の年齢でこれからの人生を考えるタイミングでもあり、これまで純粋数学を頑張って続けてきたなかで、自分なりにある程度やり切ったという気持ちが生まれたことが、大きな理由でした。お世話になった先生方とはまだまだ比べるのも恥ずかしいレベルの研究者ではありましたが、もし大学で長期的な雇用を得られたとしても、このまま続けるのは苦しいと感じてしまったのです。
そこで視野を広げて、これまで磨いてきた数理的な素養を生かして、企業で活躍する道をポジティブに検討してみようと思うようになりました。最初に就職した企業は博士人材の雇用実績が豊富な会社で、ロールモデルとなる博士人材の先輩もおり、専門性を生かしながら働きやすい環境でした。そこで出会った後藤から、のちに誘われてMiDATAの前身であるリンクバルに就職することになります。
後藤 MiDATAでは、8名の従業員のうち6名が修士以上であり、そのうち、3名が博士の学位取得者です。私が博士人材に期待するのは、専門性はもちろん、プロジェクトを完遂する能力の高さです。博士人材はキャリアの中でたくさんの「産みの苦しみ」を味わっています。この産みの苦しみは、成果物に対する責任にもつながると、私は考えています。限られた時間のなかで最大のパフォーマンスを出すにはどうすればいいかを考え抜き、「もっとやれたのに」という妥協も含めて清濁併せ呑む判断を下した経験は、ビジネスでも大きな意味を持つものです。
もちろん、大川もその素養を十分備えています。数理を専門としてきた人材は、ものごとを深く考え続けるという素晴らしい能力がある反面、目の前の課題に没頭し過ぎてしまうこともあり、その結果、コミュニケーションがおろそかになってしまう印象があります。一方で大川は、研究者としてのバックグラウンドをしっかり持っているうえにコミュニケーション能力も高く、顧客や仲間からも信頼が厚いです。私が声をかけたときには他の会社からも誘われていたようですが、当社に来てくれて本当によかったです。

後藤 大川には、これからの当社の技術をリードしてくれることを期待しています。能力は疑う余地はありません。業務に対しても真摯に取り組んでくれています。私たちが思っているはるか深くまで課題に向き合い考え抜いて、実装に至る道筋もしっかり示してくれますし、ITに詳しくないお客様にもわかりやすく伝えられる能力も持っている。彼のような人材が活躍してくれれば、もっと世の中に科学への理解、博士人材への理解が広がるのではないかと期待しています。
大川 世の中には面白い問題や難しい問題がたくさんあって、多くの企業がその解決に挑戦しています。これらの困難に立ち向かうプロジェクトにおいて、博士人材の「ひとつの問題を深く考え、解を見出してきた経験」は専門分野に依らず大いに活かせるはずです。新しい世界に飛び込む怖さはあると思いますが、少しの勇気を持てれば、活躍できる場所は大学の外にもたくさんあると思います。最後に、将来のキャリアに悩む博士人材の方々や博士課程への進学を迷っている方々の一助になれば、私としては何よりに思います。
(取材 2024年1月)