大学等
香川大学
学長特別補佐 創造工学部 副学部長
材料物質科学領域 領域長
石井 知彦 氏 博士(理学)(右)
創造工学部 材料物質科学領域 准教授
田原 圭志朗 氏 博士(工学)(左)
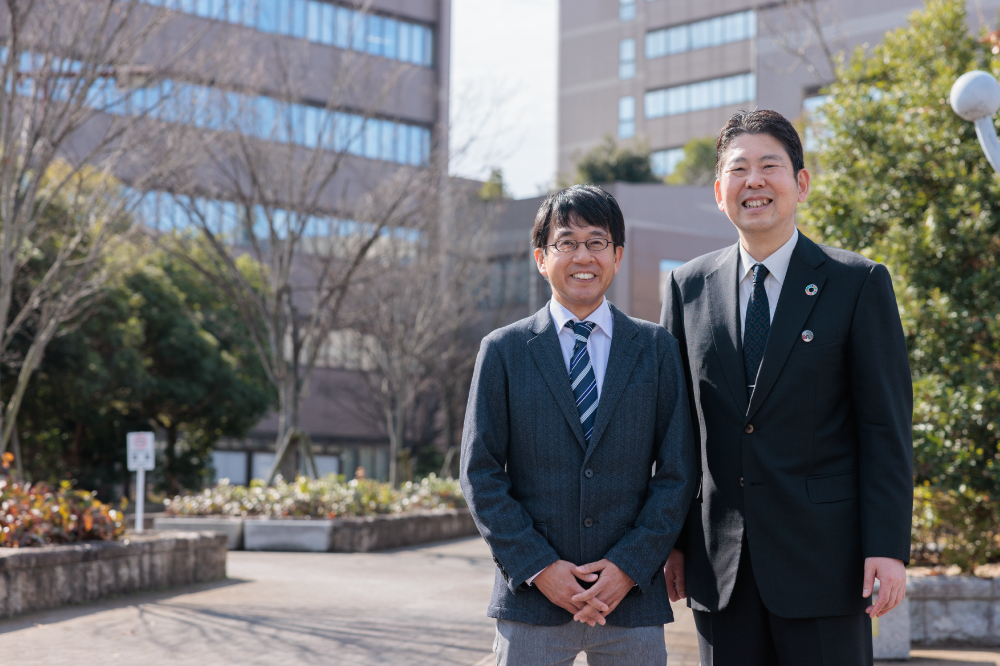
香川大学は、「持続可能な地方分散型社会の実現に貢献する人材育成と研究推進」をビジョンとして掲げ、「デザイン思考」 「リスクマネジメント」 「インフォマティクス」をテーマとした全学共通の選択科目を設置し、新たな価値を創造する人材育成に力を注いでいます。また創発科学研究科に博士後期課程が新設されたことに伴い「香川大学博士フェスティバル」を企画するなど、博士後期課程への進学促進活動にも取り組んでいます。

田原 私は2023年2月に本学に着任したので、ちょうど1年ほど勤めたことになります。現在は研究活動と並行して有機化学や高分子化学の授業を受け持っています。
前職までは助教という立場だったので、研究に専念できた反面、学部生と接する機会が少なかったのですが、本学では准教授として雇用されているので、授業を多く受け持つことで学部生と長時間接することができます。自分が教えたことが日々の演習やテストでリアクションとして返ってくることに大きなやりがいを感じています。
本学はとても素直な学生が多く、こちらが期待をかけた分、答えを返してくれます。これまでの研究室と比べても二人三脚でやれている実感が強いですね。これは都会の大きな大学とは異なる、地方大学の優れた部分なのではないでしょうか。
石井 本学は、都会の大きな大学と比べると、地方で規模も小さく、研究者同士のコミュニティづくりに関しては難しい部分があるかもしれません。しかし、素直で向き合いやすい学生が多い点は、確かに本学の優位点のひとつです。学生に教える体験を通して自らの研究を顧みられるこの環境は、研究者にとっても大きな魅力だと思います。
田原 私の専門領域は一貫して分子性物質です。いろいろな応用・デモンストレーションを行うなかで、最近は電気化学発光に注力しています。応用先としてはバイオ応用で、抗原抗体反応をキャッチできるように抗体側につける色素を合成しています。
キャリアとしては、九州大学で博士号を取得した後に奈良先端科学技術大学院大学にポスドクとして着任してそこで助教となり、5年半ほど勤めた後に兵庫県立大学に異動、そこで6年半ほど勤めて本学へ転職した形です。
転職活動のきっかけは、自分の研究室を持ちたいという思いを持っていたことです。研究のテーマを自分で決めて自分でプロジェクトを動かしていきたいという希望を持って人材募集の情報にアンテナを張っていたところ、研究室を主宰し裁量権の有る教員ポジションという本学の募集を見つけたのです。
石井 本学のような地方の国立大学の場合は予算も限られているので、大きな研究室に大勢の研究者が所属する形よりは、PIとして研究していただく形の方が、大学、教員双方にとってメリットが大きいと考えています。ポストの数も決まっており、田原の場合は退職した前任者が有機無機複合電子系化合物を研究していた准教授でしたので、まさに適任者が応募してきてくれたということになります。
この募集に対しては田原以外にも大勢の方が応募してくれました。その中には、研究実績だけ見れば田原と同等かそれ以上の人材も含まれていました。しかし田原は、人に説明する能力や、他の研究者と共同で研究できる能力がずば抜けていました。なにより模擬授業がとてもわかりやすかった。研究もできる上に、教育という形で知識を継承できる人材であるということが、採用の一番の決め手になりました。
先ほど田原が求人情報へのアンテナを張っていたと語っていましたが、大学側もどこにどんな研究者がいるのか、常にアンテナを張っています。そういった情報網のなかには田原を知っていて推薦してくれる方もいて、採用を後押しする要因のひとつになりました。
田原 転職活動の過程では選択肢を増やしたいと思って、卓越研究員事業(1)に応募して候補者になっていました。残念ながら卓越研究員事業の枠内ではマッチングに至らなかったのですが、候補者になった経験は転職活動には大いに役立ちました。
なぜかというと、卓越研究員事業では、エージェントから就職にまつわるさまざまなアドバイスをもらえるのです。そのアドバイスを参考にして、自分の研究のアピールだけでなく着任時のイメージに基づいたプレゼンをできたことが、評価された一因になったと思っています。
研究者は自分の裁量が大きい反面、自分の業績に対する責任を持たなければいけません。そしてそれをアピールする際には勇気が必要です。ですから、そんなときに誰かに相談できて違う視点からアドバイスをもらえると、とても楽になれるのです。あの相談制度はとてもいい仕組みだと思います。

石井 私は田原の採用時に初めて卓越研究員制度を知ったのですが、とても素晴らしいと感じました。助教という立場の人たちは5年間という任期のなかで実績を残さなければいけません。大学の雑務や学会の運営に携わる余裕はなく、視野を広げる機会を持つことが難しいのです。
そういった人たちが卓越研究員になれば、研究機関や大学で武者修行ができる。研究を深められるだけでなく、見聞も人脈も広げられる。これは大きな魅力だと思います。
それに、卓越研究員として認められた人材が同じ大学にいることは、学生たちへのインパクトに繋がります。自分たちも将来博士人材として認められたいと思える、そのお手本がすぐそばにいるわけですからね。
田原 キャリアパスの構築という観点では、より出会いの場を広げるといいますか、企業への就職の道も、そこからアカデミアに戻ってくる道も用意されていて、博士人材がアカデミア以外の道に挑戦しやすい雰囲気を作ってほしいのです。最近は産業界での活躍を視野に入れる博士人材も増えてきましたが、アカデミアを選んだらアカデミアで生き残らないといけないというイメージを持っている人もまだ多いです。それが払拭されれば、博士号を取得しようという学生も増えると思いますし、そのための施策を、国を挙げてやっていただきたいですね。
もうひとつ、博士人材が独力で就職活動をするのはなかなか難しい状況を理解してほしいです。大学と企業の人材交流がもっと盛んになって、大学側から博士人材に就職情報を流してくれるようになるとありがたいです。
石井 採用する側からすると、より優秀な人材を採用するためには、博士人材全体の裾野を広げることが必要だと思うのです。裾野が広がれば自然と優秀な人材も増えますからね。ある程度の選択と集中は必要かもしれませんが、一部の研究者に研究費が集中するのではなく、あまねく研究費を分配した方が、裾野は確実に広がると思います。
教育こそが人々の暮らしをよくする基礎であるという「米百俵の精神」が忘れられかけている気がしてなりません。このままでは日本の衰退を食い止めることはできませんので、国にはぜひ、教育の裾野を広げる政策を期待したいところです。

田原 若い博士人材の方々には、人と違うことに挑戦することには価値があり、それ自体が勝利だと思ってほしいですね。挑戦の先にはもちろん様々な困難が待ち構えていると思います。ですが、そこも含めて自分の選択だと考えて、価値を見出してほしいのです。どうしても踏みとどまれない場合は、今は別のキャリアを選ぶこともできます。ぜひ自分のテーマを持って、一歩を踏み出してほしいですね。
石井 博士人材の皆さんには、できるだけ視野を広く持って、いろいろな場所で武者修行していただきたいです。そして、自分自身に「できないこと」がたくさんあると知ってほしいです。それは恥でもなんでもありません。そこから、どうすればできるようになるかを模索することこそが大切なのです。そのうえで、次の世代に自分の知識や経験を伝えてください。ぜひ若い人たちのよき鑑になってほしいと思います。
(取材 2024年2月)
(1)卓越研究員事業 https://www.jsps.go.jp/j-le/index.html (参照 2024-03-26)