企業
株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR) 認知機構研究所 所長
東京大学 大学院人文社会系研究科・文学部 心理学研究室 教授
今水 寛 氏 博士(心理学)(左)
株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR) 計算脳イメージング研究室 客員研究員
東京大学 大学院情報理工学系研究科 システム情報学専攻物理情報学講座 助教
山下 歩 氏 博士(情報学)(右)
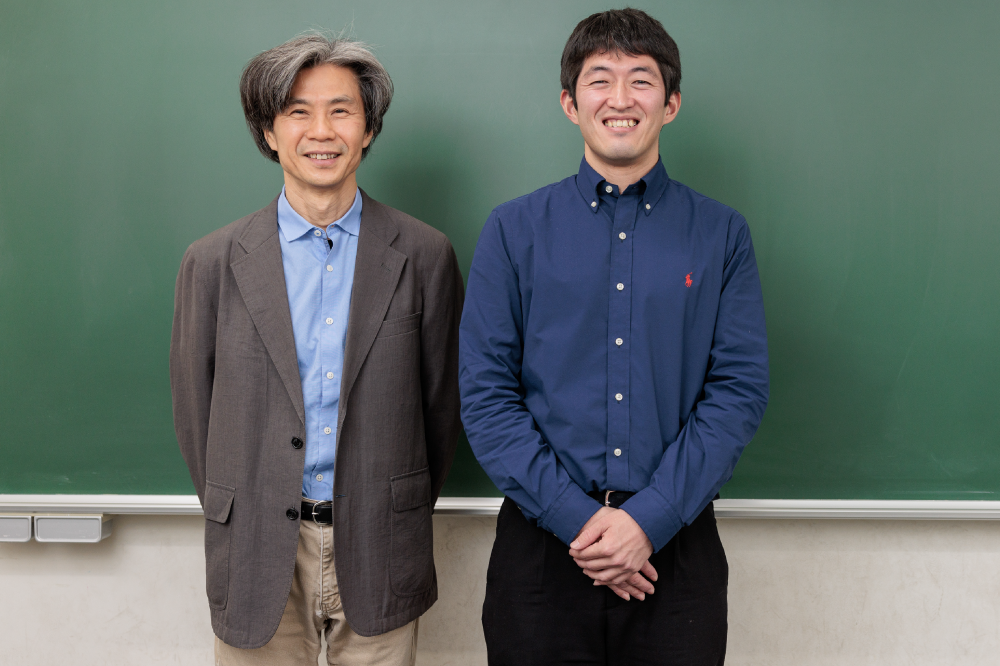
株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR)は、情報通信の先駆的な研究やイノベーションの創出を行うために、京都・大阪・奈良にまたがる「けいはんな学研都市」の中核施設として設立された研究機関です。ATRでは、「ともに究め、明日の社会を拓く」を基本理念として掲げている通り、大学や企業との共同研究や人材交流が活発に行なわれています。このアカデミアと産業界双方の利点を持つ環境では、多くの博士人材が精力的に研究活動に取り組んでいます。

山下 私は現在、ATRでは客員研究員として、東京大学では助教として、兼業で研究に取り組んでいます。東京大学では、fMRIという脳活動の計測装置を使った、集中力と神経メカニズムにまつわる研究を行っています。一方ATRでは、AIを使って脳活動から精神疾患を判別する研究を行っています。
バックグランドとしては、まず京都大学の物理工学科で機械システムを学びました。そこから不便益の研究に興味を持ち、大学院では情報学研究科に所属し、博士前期課程のプログラムでATRとの連携講座に、学外実習生として配属されたことがきっかけで、ATRでの精神疾患の研究に携わるようになりました。最初は研修研究員としてATRから給与を得ながら、その後は連携研究員として、博士号の取得を目指しました。
その頃、ATR脳情報通信総合研究所所長の川人光男先生から海外留学を勧められて、東洋紡バイオテクノロジー研究財団の長期留学制度を利用して1年間ボストンへの留学を経験したのですが、そこで自分のやりたい研究ができそうな研究室が見つかったので、日本学術振興会の海外特別研究員となり、そのままボストンで研究活動を続けながらATRの研究にも携わる生活を2年間送りました。卓越研究員事業(1)にも申請して、帰国後のキャリアに備えていましたね。
その後、ボストンに残る選択肢や他の研究機関からのお声がけもあったのですが、これからのキャリアパスを考えたときに、これまで教育や指導の経験がなく、それを得たいと思い、東京大学にお世話になることを決めました。
今水 ATRは株式会社ではあるのですが、実はアカデミアに近い特殊な企業です。応用研究も行いますが、基本的には基礎研究。研究分野は、脳、ロボット、そして通信の3つに分けられます。特に脳の分野は大学に近い基礎研究に取り組んでいるので、アカデミアとの親和性は高いと思います。
こうした背景もあり、また優秀な人材を確保するという意味でも、当社ではアカデミアとの繋がりを重視しています。山下のような人材に兼業で在籍してもらうことは、研究の質の向上と同時に、アカデミアとのパイプラインの維持にも繋がると考えています。
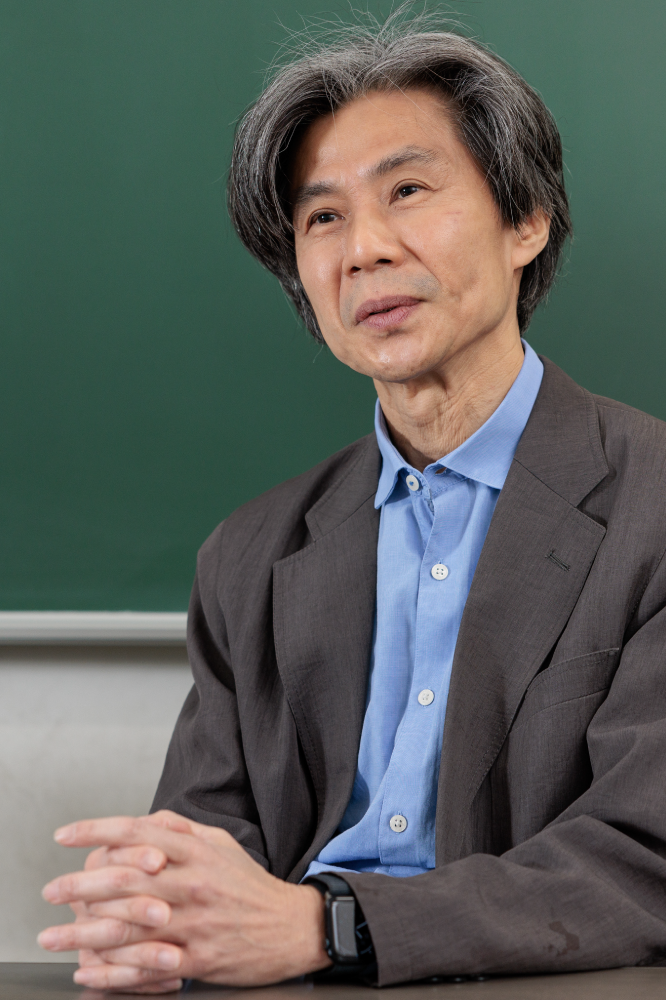
今水 私も山下と同じように、東京大学の心理学研究室で教授を本務として、ATRの認知機構研究所の所長を兼業しています。私がATRに勤め始めたのは25年ほど前になりますが、ここ10年ほどで兼業の雇用形態はかなり増えましたね。大学では、他大学の非常勤講師や学会・官公庁の委員などを兼業することは多いかもしれませんが、研究者として兼業する形は他ではあまり見られないかもしれません。
このスタイルは、研究機関にもよると思いますが、勤務時間などはそこまで縛りが厳しいわけでもなく、大学が許可している範囲であれば双方のバランスを取りながら活動できます。兼業と似た形のクロスアポイントメント制度もありますが、組織同士の契約になるので個人では動きにくい部分があるように思います。個人的には、研究者の間にもっと兼業が広まってもいいのではないかと思っています。
山下 私も同じ意見です。大学にいても共同研究はできますが、研究のやり方はあまり変わらず、収入も増えるわけではありません。企業と兼業すれば、異なる環境で研究ができて企業からの給与も入ってきますので、メリットは大きいと思います。
ただ、個人的には兼業でのバランスの取り方に少し悩んでいるところはあります。もともとあまりマルチタスクが得意ではないので、やるべきことを2つ、3つと並行して進めなければいけなかったり、そこに学生の指導も加わったりと、正直、頭が混乱してしまうこともあります。
一方で、兼業の良い面も経験しました。大学の授業でATRでの研究を紹介したところ、ある学生が興味を持ってくれたのです。その学生をATRに紹介して、これから一緒に研究を進めていけるのを楽しみにしています。兼業でなければできなかったことですし、学生に新しい知見や研究室以外の可能性を見せてあげられたことは、教員としてのやりがいを感じられる出来事でした。
大学と企業の環境の差を知ることができたのも、兼業ならではの経験かもしれません。ATRでは、PCはもちろん計算環境が整っていて、かつそれを管理してくれる人がいます。大学では教員がPCの調達から管理まですべてを自分でやらなければいけませんし、今後、ディープラーニングなどの分野では計算リソースが足りなくなる懸念もあります。整備された情報インフラと計算リソースを自由に使えるのは、研究者にとって大きなメリットだと感じています。
今水 ATRの研究は、大学での研究の大部分がそうであるように競争的資金で運営されていますが、組織としてリソースと時間をかけることで大きな金額を獲得できるので、研究者には質の高い研究環境を提供できているのではないかと思います。関西の都市部から少し離れた地域にあるので、関東や東北の学生にはあまり知名度が高くないのが課題で、もっとたくさんの博士人材にATRの存在を知ってもらいたいと思っています。インターンシップ制度などを活用して、ぜひATRでの研究を体験しに来てほしいですね。
評価基準は大学とあまり変わりません。よい研究に携わって、質の高い論文を発表していることや、採択率の低い国際学会で採択されて発表されているなどの実績、競争的資金の獲得への貢献などが、評価の対象になります。ただ、アカデミアに近いとはいえ企業なので、自分の興味と会社の方針、獲得資金の方針をうまく繋げられる資質がある方に向いている点は、大きな違いかもしれません。
山下 私が東京大学とATRで研究している集中力と精神疾患というテーマは、一見違う内容に思われるかもしれませんが、両方とも今は生物学的な基盤がはっきりわかっていないテーマで、そこに脳からアプローチするという点が共通していて、私の興味と繋がっているのです。ですから、大学ではやりたい方向に手を伸ばしつつ、ATRでは国内外からさまざまな研究分野の研究者たちと密につながって幅を広げられる。とてもいい環境で研究できていると感じています。
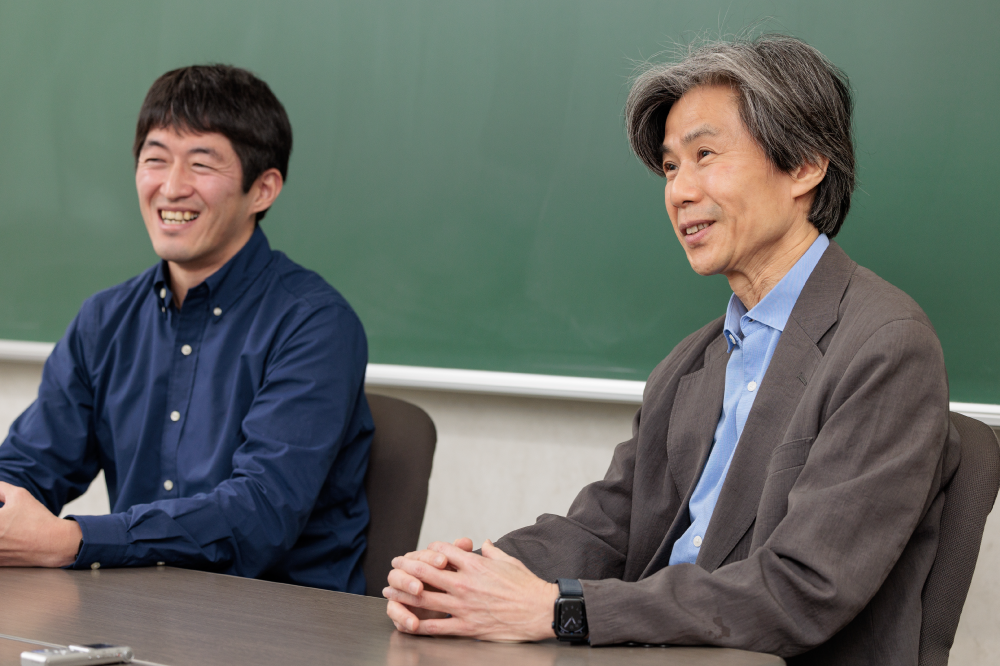
今水 ATRにいると、これまで重点的に取り組んで来た分野での質量の大きさを感じますね。長年築き上げてきた研究の実績のもとに、さまざまな人が集まってくる。大学のひとつの研究室よりは大きな広がりを持てる環境だと思います。キャリアパスとして見たときにも、ATRを経てベンチャー系の企業に行ったりアカデミアに戻ったりする人は多いです。もちろん求められる分野かどうかにも左右されますが、比較的次のキャリアに進みやすい場所だと思います。
山下 自分の場合は、次のキャリアではまずはアカデミアをベースに考えるつもりです。ただ、アカデミアに拘っているわけではないですし、現実的に生活を成立させる必要もありますから、企業に就職する可能性もありますし、もちろんATR専業になる可能性もあると思います。研究の自由度を上げるための起業も視野に入れています。
世間では博士人材の将来が悲観される論調もあります。研究分野にもよりますが、私は、実は選択肢はたくさんあると思っています。そして選択肢を掴み取るためには、一般常識に囚われずに自分の好きなことを突き詰めることが大切です。もちろんそれなりに努力や計画も必要ですが、これからの時代は博士人材もいろいろな道を選べるようになるのではないでしょうか。
今水 山下がポジティブにキャリアを選択できているのは、自分の興味の向く方向に進みながら、視野を常に広く保ってきたからだと思うのです。無駄になることもあるかもしれませんが、ひとつのことに凝り固まらずにいろいろな分野に興味を広げることは、その後の研究生活においてもきっと役に立つ経験だと思います。
そういう意味では、大学というのは多様な人や物に触れられるとてもいい環境だと思います。若い博士人材の皆さんには、研究室に閉じこもらずに、いろいろな人と話をして、いろいろな経験を積んでほしいですね。
(取材 2024年2月)
(1)卓越研究員事業 https://www.jsps.go.jp/j-le/index.html (参照 2024-03-26)