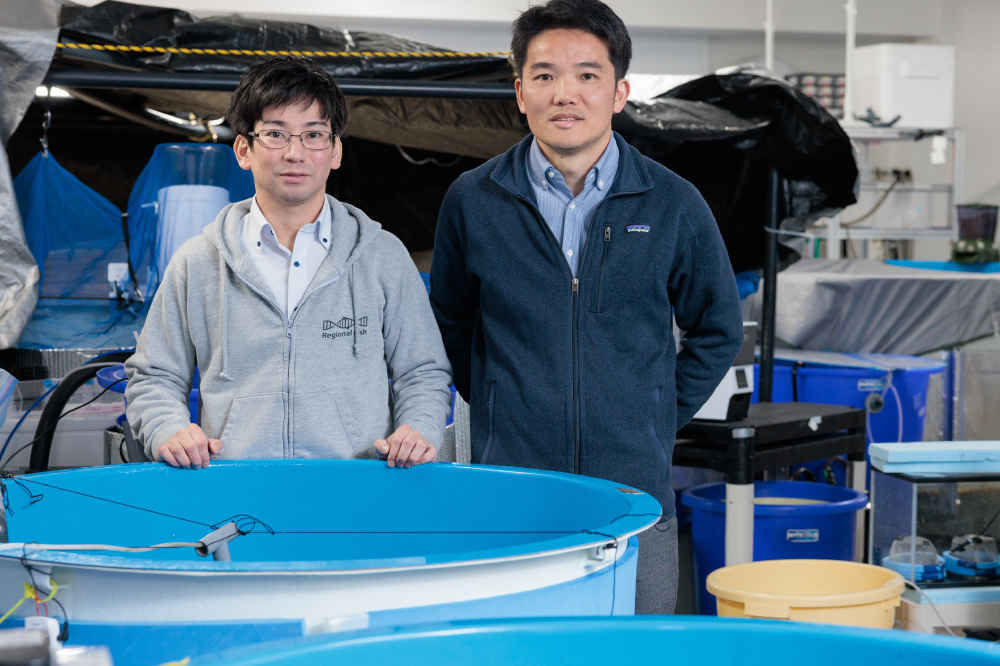企業
リージョナルフィッシュ株式会社
執行役員 研究開発部長
岸本 謙太 氏 博士(農学)(右)
研究開発部 魚類育種グループリーダー
ハットリ ヒカルド ショウヘイ 氏 博士(海洋科学)(左)
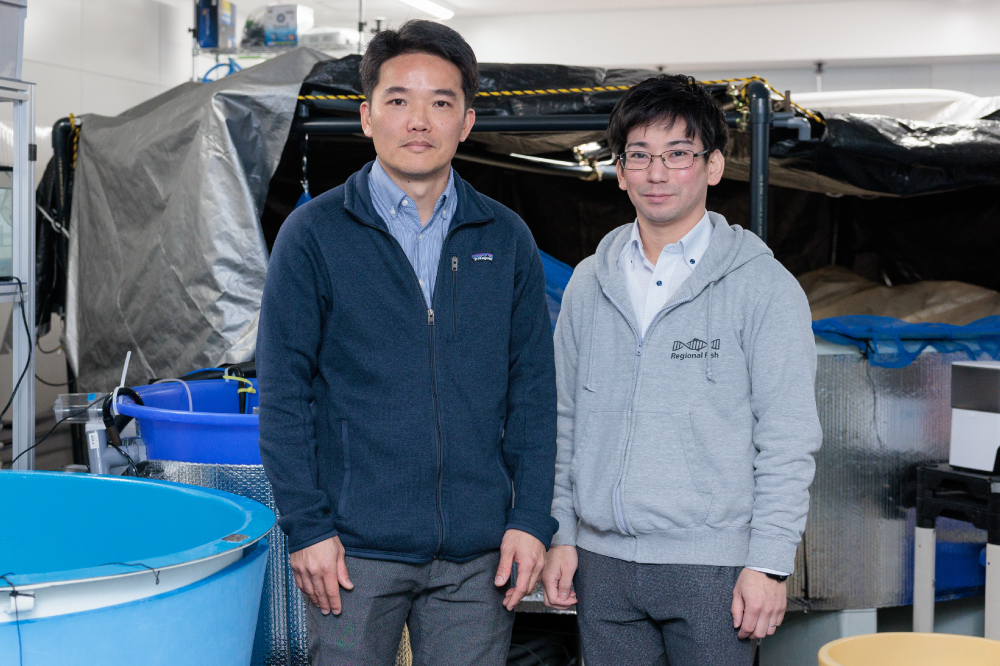
水産分野においてゲノム研究は、水産資源管理や養殖業の持続可能性などの課題を解決するための重要な位置を占めており、その現場では多くの研究人材や博士人材が活躍しています。リージョナルフィッシュは、ゲノム編集などの新しい技術を使って、魚類をはじめとした水産物の品種改良を行うベンチャー企業です。他企業との連携も積極的に行い、水産業の発展に寄与する研究開発に取り組んでいます。

岸本 当社は、コア技術であるゲノム編集技術やIoTなどを駆使したスマート陸上養殖によって養殖魚を高付加価値化し、日本の水産業をサステナブルな成長産業に変えていくことをミッションに掲げています。主な事業としては、ゲノム編集技術をはじめとする新たな品種改良技術を用いた水産種苗(稚魚)の開発や陸上養殖のアドバイザリー、自社で養殖した成魚販売などを展開しています。
私たち開発チームの主な業務は、育種開発やそのマネジメントです。自分たちの強みはゲノム編集であり、ハットリは魚類育種のスペシャリストとして当社の研究開発をリードする存在です。
ハットリ 私はブラジルの出身で、大学まではブラジルのサンパウロ大学生物学部で学び、博士課程前期から日本の東京海洋大学に所属して、そこで博士号を取得しました。その後、日本とブラジルを行ったり来たりしながらアカデミアで研究を続けているうちに、「バイオテクノロジーを使ってよい品種をつくりたい。種苗生産の現場に携わりたい。」という思いが強くなっていくのを感じました。アカデミアでは、専門性を突き詰めて論文を発表するところがゴールになりがちです。しかし、その後の応用研究にも携わりたいと思うようになったのです。
そこで前職の契約期間が終了する頃合いを見計らって、企業や海外の研究機関に絞って就職先を探し始めました。JREC-IN Portalで当社の求人を見つけたときは、自分の専門ややりたい研究とあまりにマッチしていたので、まるで運命のように感じましたね。サッカーチームをつくるなかで、足りないポジションにぴったりはまったようなイメージでした。
今は主に、アカデミア時代に成功した、高温耐性を持ったニジマスの育種技術を元に、いろいろな企業と合同でプロジェクトを進めています。自分たちがつくった品種が大手企業の養殖プロジェクトで使用されたり、消費者の元に届いたりといった形で、全体のプロセスの一部になれていること、自分たちの研究に対して社会からのフィードバックを得られることに大きなやりがいを感じています。
岸本 ハットリからの応募があったときは、優秀そうな人材だな、という第一印象でした。書類には名前がカタカナで出身がブラジルと書いてあったので、当社の事業内容からビジネスレベルで日本語が扱えないと難しいかもしれないと思いつつ面談をしたら、そこは全く問題なかったのですぐに採用が決まりました。ゲノム編集分野の人材は大勢いますが、ハットリは魚類の扱いが長く、当社が求めていた技術や知識をピンポイントで持っていたことが決め手になりました。
入社してからの活躍は期待以上のものがあります。専門分野はもちろん、幅広い視野を持って専門以外の分野にも積極的に取り組んでくれています。それから、博士の専門性とはあまり関係ないかもしれませんが、自分の手を動かすことを厭わない部分、育種に必要な特殊な水槽などを自分でつくってくれるといった貢献は、とてもありがたいです。私たちの研究では水槽はとても重要なのですが、オーダーメイドだと高額ですし、専門知識がないと的外れのものができあがってしまうこともあるのです。
ハットリ 研究するうえで、ソフトウェアである魚とハードウェアである環境、どちらも同じくらい最適化が大切ですからね。魚種が少し変わるだけで、適切な水温帯や水質、感受性が全く変わってしまいますから、水槽を含めた飼育方法に気を配る必要があるのです。特に新しい魚種を扱う際には少しずつカスタマイズしていく必要があるので、DIYはとても重要です。アカデミアでは装置を自分でつくることも多いですから、その経験が活きていると感じていますし、父親が大工だったので、その影響もあるかもしれません(笑)。

ハットリ 就職活動をするうえで、自分をアピールすることはとても重要です。研究者は、往々にしてアピール力よりも成果で勝負しようとする意識が強く、派手に自分を売るのは苦手な人が多いと思います。アカデミアであれば論文の数や所属研究室などで評価されることも多いですが、民間企業においては自分の研究がどのように展開できて、どのようなことに活かされる見込みがあるのかといった点が評価されます。私もそのあたりを意識して就職活動をしていました。
また、企業でのキャリアを考えているのであれば、自分の研究が社会でどのように役立つのかを常に考えるマインドセットが必要だと思います。私も、アカデミアで研究しながらずっとなんらかの形で養殖に携わりたいと思っていたので、自分の研究が社会全体のどこに位置づけられているのかを意識し続けていました。
岸本 企業でのキャリアを考えている博士人材にひとつアドバイスをするとしたら、基礎研究と趣味の研究は全然違うということです。応用研究につなげる思いを持って基礎研究に取り組まれているかどうかは、企業での研究に向いているかどうかを判断するひとつの指標になると思います。
正直、その方が持っている技術や研究テーマは、必ずしも私たちの業務にマッチしている必要はないと考えています。それよりも面談のときに自分の研究がこの会社でこんなところに役立てられると思う、という意思を示してくれる方のほうが、入社後に活躍してもらえるイメージを持ちやすいですね。その上で、私たちが欲しているパーツを持っていると、なお嬉しいです。
私も経営に携わるようになってからは特に、研究者が思っている社会実装と市場が求める社会実装の違いを感じています。自分たちがベストだと思ってつくった魚が、実際に市場に出してみると違うニーズを引き出し、そのフィードバックから始まるのが企業の研究であり、そこに対する戦略を練ることが重要だという点を、アカデミア出身のスタッフに理解してもらいながら、プロジェクトを進めるようにしています。
ハットリ 私は、日本のイノベーションを加速させるためには、もっとベンチャー企業が増える必要があると思っています。例えば京都大学では、イノベーションセンターがあったり、京大桂ベンチャープラザに多くのベンチャー企業が入居していたりするので、博士人材はベンチャー企業と比較的容易に接点を持つことができます。こうした動きがもっとアカデミア全体に広がると、博士人材がベンチャー企業で活躍する未来を描きやすくなり、起業という選択肢も増えると思うのです。せっかく優秀な人材なのに既存企業に入るとそれまでと全く違う分野の研究をせざるを得ないようなケースもあり、それはとてももったいないことだと思います。もっと、優れた研究をビジネスとして世に出しやすい環境ができるといいですね。
岸本 業界としては、優秀な人材が不足していると感じています。当社としても常に募集はかけているのですが、こちらが求めているような人材からの応募はなかなかありません。企業での研究職は多くの場合パーマネントで働けますから、比較的身分を保証できる傾向は強いと思いますし、研究環境も整っています。当社も、研究費はかなりのボリュームで確保できています。4年半で27億円という農林水産省のスタートアップ基金にも採択されたので、今後は市場導入までの大規模実証プロジェクトを進める予定です。もちろん優秀な人材は積極的に採用していく方針です。
当社は2019年の設立で、まだアーリー期のベンチャーです。ベンチャーというと、技術自体は確立されていてあとはビジネス展開に力を注ぐケースも多いですが、当社の場合、水産業全体への貢献を考えると、可食部増量マダイなどすでに技術を持つ品種以外の魚類や無脊椎動物などにも展開していかなければいけないと考えています。ですから、まだまだ自分で研究プロジェクトを立ち上げて考えを深め、研究を進めていくことができる人材が必要です。
ハットリたちが入社した2021年は横展開を見据えた転換期で、同時に5名の博士人材を採用しました。今は20名以上の博士人材が所属しており、さらに人材を募集しています。ぜひ、新しいことへのチャレンジを厭わない、アントレプレナー的な思想を持っている方に参画してほしいですね。
(取材 2024年2月)