大学等
室蘭工業大学
大学院工学研究科もの創造系領域電気電子工学ユニット教授
川口 秀樹 氏 博士(工学)(左)
大学院工学研究科もの創造系領域電気電子工学ユニット 准教授
趙 越 氏 博士(マテリアルサイエンス)[卓越研究員](右)
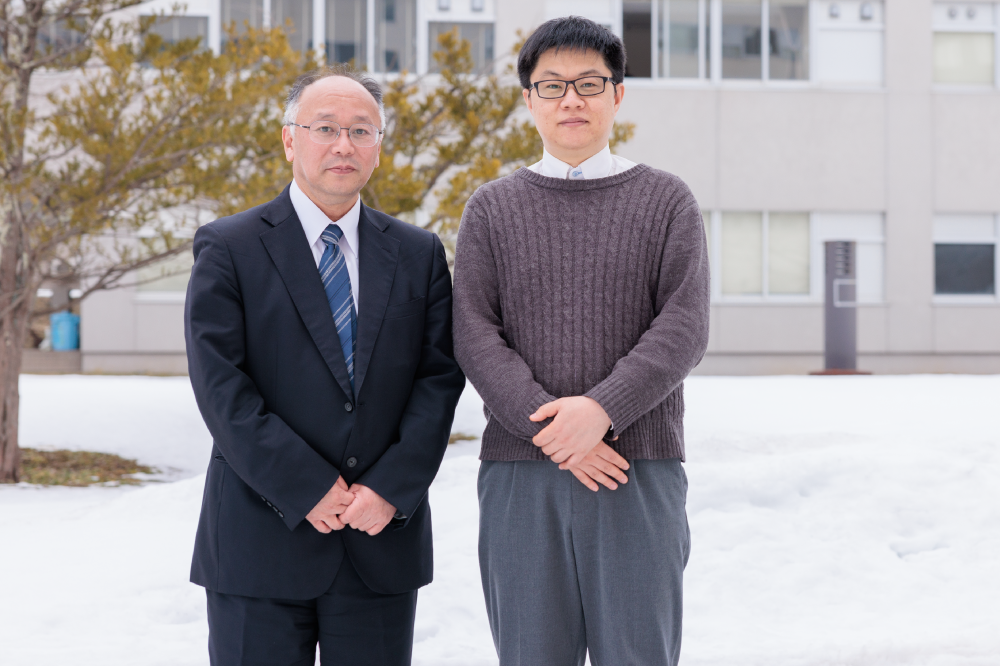
国立の工業大学である室蘭工業大学は、専門×情報の素養を持つ科学技術者の養成に力を入れており、朝日新聞出版の「大学ランキング2024」の各部門で論文引用度指数が上位にランキングされるなど、確かな研究力をベースとした教育力を強みとしています。「北海道MONOづくりビジョン2060」を掲げて、北海道、そして日本を支える研究人材を輩出するべく、2019年には理工学部を新設。大学院教育の充実も進めています。

趙 私は本学のもの創造系領域、電気電子工学ユニットで准教授を務めておりまして、5年間のテニュアトラック雇用で、2023年4月から独立の研究室を持っています。研究内容としては、光工学を柱としながら、非線形光学、分光法やイメージングなどをカバーしています。5年ごとに研究計画を立てており、今後は量子干渉、量子光源の開発に力を入れるつもりです。
教員としては、今は大学院生ひとりを担当していますが、来年度からは学部4年生数名が配属される予定です。博士学生を積極的に応援したいと考えており、日本人学生はもちろん、海外の大学からの留学生もどんどん受け入れ、グローバルな研究室を作りたいと思っています。
ここに至るまでの経歴は、2017年12月に北陸先端科学技術大学院大学で博士号の学位を取得して、2018年から工学院大学にポスドクとして所属し、2年間、質量分析をテーマにした研究活動に携わりました。その後豊田工業大学のレーザ科学研究室にポスドクとして参画し、中赤外超短パルスや中赤外分光イメージングをテーマとして3年間。そして2023年に本学に雇用という流れになります。
次の就職先を探す際にはJREC-IN Portalを利用することが多かったのですが、そこで卓越研究員事業(1)を知りました。公募を見ていると卓越研究員候補者のみという条件の枠もあり、パーマネントポジションも多かったので、卓越研究員になればキャリアの選択肢が広がると考えて申請しました。本学の公募でも卓越研究員候補者が対象とされていたので、応募できた形です。
川口 本学では、多くの場合、各学科・コースの事情、状況を鑑みながら、学長が主導する進め方で必要な人材を募集、採用しております。本学は総合工科大学ですから、学生に人気がない分野でも、長期的な視点で、将来、社会から必要とされるときのために研究の火を絶やすわけにはいきません。ですから、各学科・コースの事情を考慮してバランスよく人材を採用する必要があります。
ちょうど趙が応募してきた昨年度は当ユニットで卓越研究員を採用する方針が学長から示されていたため、それに沿って公募を出していた次第です。本学では趙の前にも何名か卓越研究員を採用しており、彼らが高い能力を持っていることはわかっていました。
なお本学の選考においては、研究能力はもちろん、教育や学会運営などの資質も考慮されます。大学の教員の場合、小中高の教員試験のように、教育、学生指導等に関して体系的にトレーニングを積む機会はありませんし、最近は特に、学生のメンタルケアも教員の大切な役割ですので、そのあたりの適正も重要になります。
趙 私の場合、ポスドク時代も学生のケアをすることはありましたし、授業自体は経験がなかったのですが自信はあったので、そのあたりをアピールしたことが採用に繋がったのではないかと思っています。
趙 私は子どもの頃から研究者になることが夢でした。当初は自然科学に興味があったのですが、2008年、3名の日本人研究者が素粒子に関する研究でノーベル賞を受賞されたのを見て、将来は物理の道に進もうと考えました。学部時代は経営工学を中心に学んでいたのですが、研究室の配属時に学科の先生に相談して、別の学科の光学を学べる研究室の配属にしていただきました。そこで量子光学の研究をスタートしました。その後大学院でも光工学の研究を続けました。
アカデミアで研究を続けたい気持ちは持ち続けていたのですが、ポスドク時代にはなかなか次の職場が見つからず、企業への就職も選択肢に入れるようになり、豊田工業大学の任期が切れる際には企業も含めて就職先を探しました。
結局企業に就職することはなかったのですが、そういった不安定な環境でも私がこれまで研究を続けてこられたのは、自分の中に柱は持ちながらも、ある程度幅広く、異分野にも挑戦して、その分野の流儀や研究スタイルを取り入れてきたからだと思っています。
ずっと同じ分野に収まっていると、どうしても視野が狭くなってしまいます。研究者は研究予算を確保することも仕事のひとつですから、さまざまな視点を持ち、話題になっている分野や国が重視する戦略などと自分の研究との関連性を見つけ出すことで、採択される確率の高い研究計画を立てられるのです。
私がこれまで師事してきた上司は予算の取り方が上手な方ばかりでした。自分もこれから独立した研究室を持つので、やりたい研究を続けるためにも、予算の獲得に力を入れなければなりません。

川口 本学が必要としているのは、研究とヒューマンスキルのバランスが取れている人材です。場合によっては多少の偏りがある方でも活躍できることもありますが、どちらかが優れていてももう一方が見劣りしてしまう方だと、日本の技術を支える人材を輩出しようとする本学の理念からいずれ外れてしまいます。ですから、面接ではご本人が話にくいことを聞く場合もあります。そこで遠慮してしまうとお互いのためによくないですからね。
また別のパターンとして、企業から来られる方もいますし、企業出身者を念頭においた公募をかけることもあります。その場合は、外部資金の獲得経験や共同研究といった実務経験も大切になります。
趙 私も企業との共同研究の経験はありますが、応用や商品開発を重視する企業のニーズと、研究者が考える研究テーマのギャップを知ることができた経験は、今でも役に立っていると感じます。先ほども申し上げましたが、博士人材の皆さんには、視野を広げて積極的に異なる分野を経験することをお勧めします。それから、若いうちから業績をどんどん上げること。領域にも拠りますが、私の経験だと年に3本は論文を出さないと、アカデミアでポストを得続けるのは厳しいのではないかと思います。
川口 採用する立場から言うと、採用された後の方が期間が長いということを考慮しながら、キャリアプランを考えてほしいですね。30代で雇用されたとすると残りのキャリアは約30年間。その間、さまざまな学生を担当して、それぞれに研究テーマを持たせて、アウトプットまで導かなければなりません。毎年毎年、担当学生に、その分野では自分がスペシャリストであるという自信を持たせて送り出す。しかも自分の研究を続けながら、また論文を書き続けながら。大学学内の入試業務等の運営、さらに社会貢献として各種学会の運営なども大切な仕事です。これを30年間続けることを考えれば、常に学び続ける必要がありますし、趙が言っているように、若いうちから異なる分野にも手を広げておくことが大切だと思います。
(取材 2024年2月)
(1)卓越研究員事業 https://www.jsps.go.jp/j-le/index.html (参照 2024-03-26)