大学等
秋田大学
国際資源学研究科 教授
縄田 浩志 氏 博士(人間・環境学)(右)
国際資源学研究科 助教
後藤 真実 氏 博士(アラブ・イスラーム学)[卓越研究員](左)
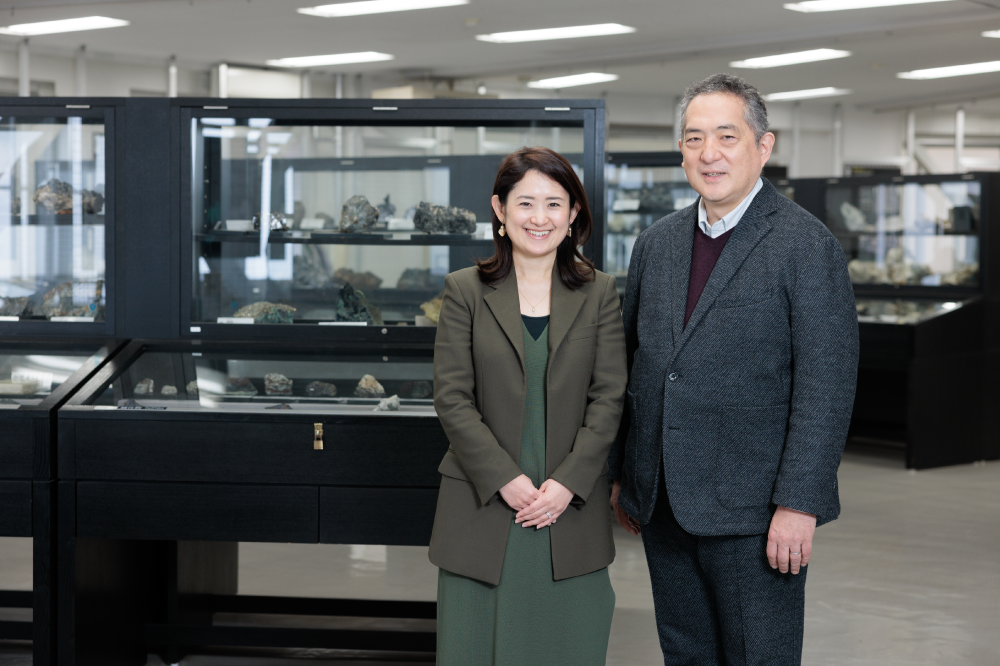
秋田大学は、世界を視野に入れた4つの学部と大学院のシームレスな教育体制により、多くの優秀な人材を輩出。世界と実学を見据えた教育を志向しています。近年はグローバル社会への対応力を伸ばすために、全学的なTOEICの受験サポートや海外留学制度など、英語教育施策にも力を入れています。それぞれ特徴を持つ4つの学部のうち、国際資源学部は我が国随一の資源を対象とした学部として、文理双方のグローバル資源人材養成に取り組んでいます。
国内唯一の資源学部に卓越研究員事業(1)を活用して就職

縄田 秋田大学は、歴史的に地下資源の発見と開発という研究の柱を持っており、その実績や人材を集積して2013年に設立されたのが国際資源学部です。資源学は国際的な活躍が求められる学問ですので、専門科目の授業はすべて英語で行われ、理学、工学に加えて人文学、社会科学の教員が文理融合型の教育カリキュラムを提供しています。
また、海外フィールドワークをカリキュラムに組み込んでいる点も特徴的です。すべての学生が、指導教員に引率されて世界中のさまざまな場所に散らばり、1ヶ月ほどのフィールドワークを経験してから社会に出ていくというのは、非常にユニークだと思っています。
我が国唯一の“国際資源”をかかげた学部ですので、所属教員には高い専門性が求められます。卓越研究員事業にも公募を出しており、退職される先生のいる資源政策コースで若手の博士人材を募集していたところ、後藤先生に応募していただいた形になります。
資源という対象は、文系的な視点が加わることでより発展できるポテンシャルを秘めた分野だと考えています。一方でエネルギー資源や鉱物資源といった分野を人文学・社会科学的な立場で研究している研究者はそう多くありません。かつまだ年齢も若く、本人の今後のキャリアパスに役立つ実績を積んでいただける。そういう意味で、後藤先生はまさに私たちが求めていた人材像に当てはまる方でした。
後藤 私は博士課程では主に中東、特にペルシャ湾岸地域の女性の服装に関する研究をしていました。学部では法学を学んだのですが、学部3年生のときにアメリカに留学した際、中東系の人たちが現地で差別的な扱いを受けているのを見て大きなショックを受けました。そのような偏見をなくす仕事に就きたいと思い、最初は外交官を志しました。
外務省で短期雇用の非常勤職として1ヶ月ほど勤務したのですが、自分が思い描いていた仕事とは少し違うと感じて、クウェート大学に留学してアラビア語を学び、続けてカタル大学でも語学を学んだのちにそのままカタル大学の大学院に進学、湾岸地域研究専攻で修士号を取得してから湾岸地域研究の世界的な中心であるイギリスのエクセター大学でアラブ・イスラーム学の博士号を取得しました。その後東京外国語大学にポスドクとして3年間所属し、日本学術振興会の海外特別研究員に応募してニューヨーク大学アブダビ校に着任したのですが、そのタイミングで秋田大学が卓越研究員を公募していることを知って応募した次第です。
もともと、どこかの大学に腰をすえるというよりはポスドクとして自由に研究活動を続けたいという思いがあったのと、2年間はアラブ首長国連邦にいるつもりだったので、任期なし採用での国内就職というキャリアを選ぶかどうか迷ったのですが、家庭の事情や年齢を考慮すると、このタイミングで定職に就いておいた方がいいだろうと判断しました。
卓越研究員事業では大学に所属していても50%は研究活動に携わるという規定があるので、大学と交渉して、初年度の秋まではアラブ首長国連邦で研究をして、その後秋田大学に戻って来る条件で採用を決めていただきました。ですから実質、秋田大学での勤務は2023年の9月からですね。
女性活躍のために実情を踏まえた制度設計を
縄田 教育と研究を担う大学に所属する私の観点からよかったと思っているのは、後藤先生と退職される先生が所属する期間がオーバーラップしていたことです。これまで本学に所属して研究活動されていた先生の姿を、教育や管理運営業務も含めて後藤先生に見ていただくことができた。経験のある先生から教わっておけば今後戸惑うことは少ないでしょうし、後藤先生も積極的に学び取ろうという姿勢を見せてくれています。今回はタイミングがよかったのでこうした期間が取れましたが、今後の採用活動でも、できればこうした形で引き継ぎ期間を設けられるといいのではないかと思っています。

後藤 本学で働くうえで多くのことを学ばせていただきましたし、退職される先生は女性なので、女性研究者としても学ぶことは多かったです。アカデミアにおける女性研究者の支援体制は整って来ているとはいえ、まだ足りない部分はあると思っています。国から支援を受けて研究している以上は業績を上げなければいけないプレッシャーもありますから、妊娠や出産といったライフイベントとの両立に二の足を踏む女性研究者は多いのが現状だと思います。
私の場合も、コロナ禍で予定していた海外調査や国際学会に行けなくなり、国内で在宅勤務を半ば強制されるような状況にならなければ、テニュアが取れていない不安定な状況で、子どもを産もうという決心はし辛かったかもしれません。海外にフィールドワークに行くことも多いので、子どもを保育施設に預けるコストや、現地への子どもの同行について支援が受けられるかどうかは、研究成果に大きく関わってきます。
女性研究者に限らず、研究を続けたい研究者が長期にわたって活躍できる環境ができれば、自ずと日本のアカデミアも活性化すると思うのです。
縄田 女性に活躍してもらうためには大学側も環境の整備を進める必要がありますね。後藤先生のような経歴をお持ちの方が本学に着任してくれたことは、本学にとっても大きな意義があります。若手や女性研究者の意思が組織全体に広がって行くよう支援したいし、環境を変えていく局面での若手研究者の皆さんの活躍を期待したいですね。
若手の活躍という意味では、大学側の評価軸も再考する必要があるとは思っています。当然雇用する大学としては一定のルールのもとで研究業績を測るわけですが、現状だと理系的な要素が強いのが課題です。掲載論文数やTHE日本大学ランキングの評価に直結するような基準でいえば、後藤先生の業績は必ずしも抜きん出ているわけではありません。後藤先生の志向と大学として目指す方向性とが合ったからこそ採用に至ったわけで、そうした定性的な評価軸も大切にすべきだと思います。
自分の強みを理解して相手に合わせて活用することが大切

縄田 博士人材の皆さんに、採用する側の立場として、そして皆さんと同じくひとりの研究者として自分を組織にアピールして職を得てきた立場からアドバイスするとすれば、専門分野についてはもちろんのこと、応募した先で自分の能力をどのように活かせるかをよく考えてほしいですね。そしてそれを相手にうまく伝えられるかどうかで、評価は大きく変わると思います。たくさんの申請書類にふれる機会があると、組織を理解しているかどうかはある程度読み取れるようになりますからね。
後藤 中東で研究活動をしていると、日本人であること、女性であることの強み、ありがたみを感じることが多いのです。日本は戦後に経済発展を遂げた国であり、優れたアニメや電化製品を生み出す国として尊敬を受けているので、フィールドワーク先でもとても歓迎されます。また、生活に深く関わる研究なので、女性だからこそセンシティブな質問にも答えてもらえる場合があります。就職活動でもそれは同じだと思っています。自分の強みはなんなのかを理解して、それをうまく利用することが大切だと思います。
それから、キャリアを構築するうえでは、人脈があるかどうかはとても大きな意味を持ちます。私の場合は法学という畑違いの分野から移ってきて、さらに海外で活動することが多かったので、日本のアカデミアにコネクションがほとんどありませんでした。一方で、中東地域研究やイスラーム研究の分野において日本人研究者はかなり重宝されると感じています。そこで、この先国際的な舞台で競争していくためには自分が日本人であることをひとつの武器にできるのではないかと思い至り、積極的に人脈をつくることを考えました。
若手の研究発表会に参加したり、中東研究のプロジェクトに応募したりするうちに人脈が広がって、本学に就職できたのは、日本のアカデミアで活動の幅を広げていたことも影響していたのではないかと思っています。博士人材の皆さんにも、人脈づくりには意識して取り組んでみてほしいと思います。
(取材 2024年3月)
(1)卓越研究員事業 https://www.jsps.go.jp/j-le/index.html (参照 2024-03-26)