企業
社会での経験は、研究にとってもいいフィードバックになる
株式会社アイデアファンド
代表取締役 CEO
大川内 直子 氏(左)
九州産業大学
国際文化学部 講師
川松 あかり 氏(右)
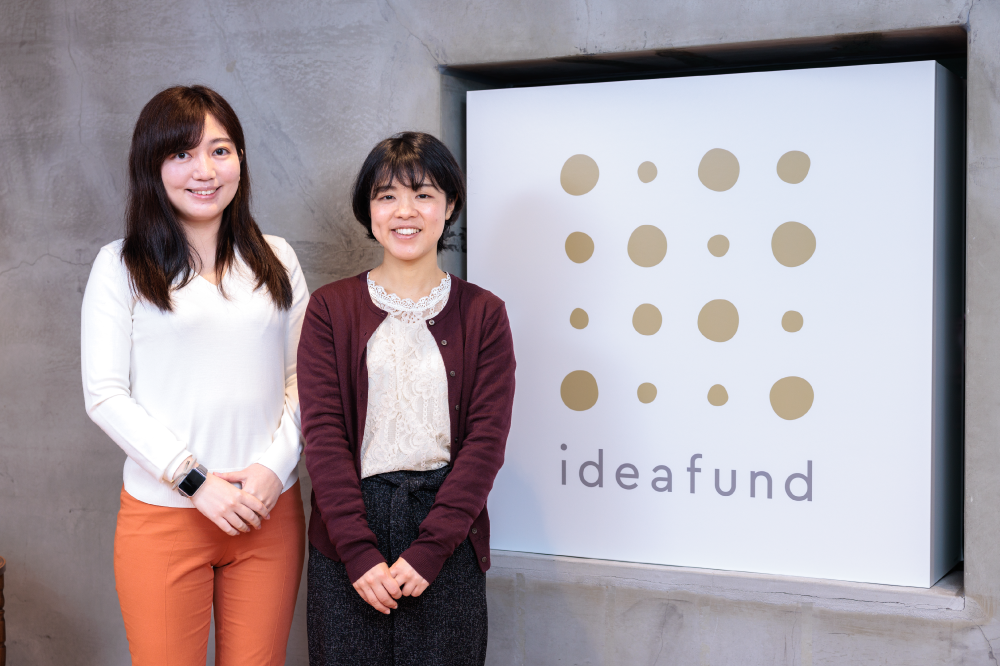
「アイデアで資本主義を面白く」をコーポレートミッションとして掲げる株式会社アイデアファンドは、文化人類学の調査手法を応用した独自の方法論に基づくリサーチ&アナリシスを提供するベンチャー企業です。徹底的な観察からユーザーの無自覚なニーズを引き出す同社の手法は、ユーザーの本質的なインサイトを得たい多くの企業から注目を集めており、その基盤となる調査や分析には、博士人材の知見やノウハウが活かされています。
文化人類学のアプローチを応用して企業の課題を解決する

大川内 当社は2018年の創業以来、文化人類学的な手法を用いたリサーチを行い、その結果をクライアントにお届けするビジネスモデルで運営してきました。リサーチの領域には量的調査と質的調査のふたつがあるのですが、当社では質的調査を重視しています。
従来のマーケティングリサーチでは、アンケートなどの量的調査が中心となります。アンケート調査はすでにある商品の満足度などを広く知るのには適していますが、対象者の無意識や潜在的なニーズに迫るのは難しいため、近年は従来型のマーケティングリサーチの結果を元にヒット商品やイノベーションに結びつけるのが難しい点が企業にとってのジレンマになっていました。
一方で、当社が行う質的調査では、対象者を深く理解し、彼らが本当に求めているものを追求します。そこには文化人類学的なリサーチ手法が応用されており、私の出身である東京大学の博士課程と修士課程に在籍している学生の皆さんにも、設立直後から調査や分析を担当してもらっています。
このスキームによって、依頼企業は自社の顧客や潜在的なユーザーについて、表面的な理解にとどまらない深い洞察を得ることができ、博士課程の学生も研究を続けながら収入を得られる。そして当社の事業も成長できるという、Win-Winの関係を築けると考えています。
川松 私も東京大学の博士課程で学んでいたときに声をかけていただいて、インタビューとその結果を分析する仕事を経験させてもらいました。当時は博士課程の7年目で、博士論文を書かなければいけない時期だったのですが、経済的な余裕もなかったので、自分の専門性を活かす機会というよりは、ありがたいアルバイトくらいの感覚で引き受けたのを覚えています。
ところが、実際にお仕事として経験してみると思った以上の充実感がありました。普段接することのない人たちのお話からたくさんの知識や洞察を得られたこと、そして企業のプロジェクトの一員として社会から必要とされている実感を得られたことは、博士論文の進行に行き詰まってひとりで悩んでいた当時の私にとって、とても大きな救いになった気がします。
文化人類学の研究においては、地域に溶け込んで調査し、そこに住む人たちから情報を得るフィールドワークが重要な要素のひとつなのですが、調査方法はほとんど自己流なので、それまでインタビューの技術を褒められるといった経験がありませんでした。ですから、アイデアファンドで実施したインタビューを大川内さんや会社の皆さんから評価していただけたことは、なにより励みになりました。
プロジェクトに参加して、社会へ出ることにポジティブなイメージを持てた
大川内 私は大学院生の頃、経済的に苦労している先輩の姿を間近で見ていました。私自身を顧みても、経済的な不安から博士後期課程に進まなかったという事情があります。ですから、生活の糧になりつつ、かつ博士人材の専門性も活かせる場所を提供したいという気持ちがあり、そういう場所にこの会社がなれるといいと思っています。
採用活動としては、基本的にはプロジェクトを遂行するにあたって社内の知見だけでは難しいと判断した場合に、内容によって適任と思われる方に声をかける形です。ほとんどの場合、私がその人の発表を聞いたことがあったり論文を読んだことがあったり、研究内容に惚れ込んでいる方が対象となります。皆さん一番大切なのは研究ですから、学会発表や論文執筆など研究活動の状況にはできるだけ配慮して依頼するようにしています。また、なかにはビジネスシーンが苦手な人もいるので、その場合には社内の人間がサポートすることもあります。

川松 私は現在、九州産業大学に日本文化学科の講師として勤務しています。学生時代には福岡県でフィールドワークをしており、今でもその頃からの研究を続けているので、JREC-IN Portalで公募を見つけて、勝手に自分にぴったりだと思ってしまいました。任期のないテニュア採用ではありますが、フィールドの近くであることが私にとって最も大きなメリットだったので、勤務形態や今後のキャリアには、実はあまり執着はしていません。
文化人類学を専門とする人たちは、ずっと大学に所属して研究を続けるのが基本で、社会に出て働くイメージを抱きにくい環境にいます。それどころか企業の経済活動に参加することに対して、研究者としての倫理という観点から慎重にならざるを得ないところもあると思います。私自身もそういう傾向があることは否めません。ただ、私はアイデアファンドでプロジェクトに参加した経験を経て、企業活動との接点を持つことにポジティブなイメージを持てました。後輩の皆さんには、もっと視野を広げて多くの選択肢を持ってもいいのではないかということをお伝えしたいと思います。
大川内 社会に出て成果を出す経験は、研究にとってもいいフィードバックになると思うのです。例えば当社でのプロジェクト参加のような経験も、自分のフィールドと100%同じではなくても「自分がやってきたことが誰かの役に立つ」経験だと考えて、もっと挑戦してみてほしいですね。
川松さんが言うように、文化人類学では、博士課程を年限いっぱい使うくらいフィールドワークや博士論文の執筆に時間をかけざるを得ない人がたくさんいます。そうなると、学位を取得する頃には30代も半ばになって、社会に出るに出られないという現象が起きてしまう。
学位取得までの期間を短くしようという議論もあるようですが、それは研究の質が損なわれることとトレードオフになってしまう恐れがあり、非常に難しい問題です。我が国の国力を上げるために博士人材を増やそうという動きは理解できるものの、すべての学問領域を同列に語るのは乱暴ですし、無責任にも感じられます。行政や大学が、もっと入り口のところで適性を見る、他の選択肢を示すといった支援を提供することも必要なのではないでしょうか。
また当社としても今後、専門知識を持った人材が自身の知識やスキルを活かしながら将来のキャリアにもつながるような働き方や、当社での経験が大学や研究機関に評価してもらえるような取り組みを考えていきたいと思っています。
(取材 2024年3月)
