|
■1. 技術者と環境倫理■
Q1.地球の有限性が世界的に認識され始めたのはいつ頃ですか? Q2.公害問題には具体的にはどのような問題があるのですか? Q3.1992年に開催された地球サミット(環境と開発に関する国連会議)について教えてください。 Q4.環境基本法の概要を教えてください。 Q5.ブルントラント委員会とはどのような委員会なのですか? ■2. 地球温暖化■ Q6.IPCCは何をする組織ですか? Q7.なぜ人為的に排出されたCO2などの温室効果ガスが地球温暖化の原因といえるのですか? Q8.温室効果が最も強い温室効果ガスは、水蒸気ではないのですか? Q9.地球温暖化の将来への影響は、地球全体でどこでも同じですか? Q10.地球温暖化問題に対する対策として予防原則を用いることが決まったのはいつからですか? Q11.地球温暖化問題について、科学者にはどんな対立があるのですか? Q12.適応策を適用する場合の注意点にはどのようなことがありますか? Q13.日本では太陽光発電の買取についてどのような制度になっていますか? ■3. 生物多様性■ Q14.生物多様性は生物の種数のことではないのですか? Q15.生物多様性という言葉は、いつ頃から使われているのですか? Q16.生物多様性はどれくらいの速さで低下しているのですか? Q17.生物多様性を数値化することはできるのですか? Q18.「自然の権利」の考え方は古くからあるのですか? ■4. 化学物質と環境リスク■ Q19.四大公害には水俣病のほかに何がありますか? Q20.「予防原則」は「未然防止」とはどう違うのですか? Q21.「化審法」で規制されている化学物質の種類はどのように管理・公表されていますか? Q22.化学物質を対象とした法律はほかにどのようなものがありますか? Q23.化学物質の毒性を定量的に把握するにはどのようにするのですか? ■5. 循環型社会と資源・廃棄物■ Q24.我が国の物質フロー指標はどのように推移しているのでしょうか? Q25.昭和30年代の社会と現代の社会が異なる点の本質はどこでしょうか? Q26.循環型社会を支える国際条約にはどのようなものがあるのでしょうか? Q27.現在、廃棄物発電で回収されている電力はどれ位でしょうか? Q28.インセンティブを促す制度とはどのような制度をいうのでしょうか? ■6. 低炭素社会とエネルギー■ Q29.日本は化石エネルギーにどの程度依存しているのですか? Q30.森林等を耕作地に変えてエネルギー作物を栽培している具体例はありますか? Q31.再生可能エネルギーには太陽光発電や風力発電のほかに何がありますか? Q32.省エネや再生可能エネルギーの普及にはどのように取り組めばよいですか? Q33.低炭素社会の具体的な実現イメージについて教えてください。 ■7. 環境コミュニケーション■ Q34.実際に、どのような方法で環境コミュニケーションが行われているのですか? Q35.専門家と住民が情報を共有するため、どのような機会があるのですか? Q36.分かりやすく伝えるとは、具体的にどのようなことをすればいいのですか? Q37.実際にどのような環境教育が行われているのですか? Q38.地球温暖化問題では、どのような利害関係が生じるのですか? ■1. 技術者と環境倫理■ Q1 地球の有限性が世界的に認識され始めたのはいつ頃ですか? A1 ローマクラブが1972年に発表した「成長の限界」で、人口の増加と産業がこのまま成長を続けると、天然資源の枯渇や環境汚染により100年以内に成長は限界点に達するという報告を発表した時期です。また同年にはストックホルムで国連の人間環境会議が開催されました。この会議のテーマは「かけがえのない地球」であり、環境問題が地球規模、人類共通の課題であることが認識され、「人間環境宣言」や「環境国際行動計画」などが策定されました。 Q2 公害問題には具体的にはどのような問題があるのですか? A2 環境基本法第2条第3項に列挙されている大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭、地盤沈下の7つが典型七公害と呼ばれています。このほかにも光害や日照に係る被害などを公害に含めることがあります。 Q3 1992年に開催された地球サミット(環境と開発に関する国連会議)について教えてください。 A3 1992年6月にブラジルのリオデジャネイロで開催された首脳レベルでの国際会議です。地球サミットと呼ばれています。人類共通の課題である地球環境の保全と持続可能な開発の実現のための具体的な方策が話し合われました。その成果として、「環境と開発に関するリオデジャネイロ宣言(リオ宣言)」、「アジェンダ21」、「森林原則声明」が合意されました。さらに、「気候変動枠組み条約」と「生物多様性条約」が採択されました。 Q4 環境基本法の概要を教えてください。 A4 1993年(平成5年)に制定、施行されました。環境関連分野について国の政策の基本的な方向を示した法律です。いわば環境の保全に関する憲法といえる法律です。具体的な内容は、環境の保全に関する基本理念、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務、環境の保全に関する施策の基本となる事項などです。 Q5 ブルントラント委員会とはどのような委員会なのですか? A5 1984年国連に設置された「環境と開発に関する世界委員会」(WCED)のことで、委員長がブルントラント氏であったことから、その名前をとってブルントラント委員会と呼ばれました。この委員会でまとめられた報告書"Our Common Future"(地球の未来を守るために)では、環境保全と開発の関係について「将来世代のニーズを損なうことなく現在の世代のニーズを満たすこと」という「持続可能な開発」の概念を打ち出しました。 ■2. 地球温暖化■ Q6 IPCCは何をする組織ですか? A6 IPCCは世界気象機関と国連環境計画により1988年に設立されました。IPCCの使命は、地球温暖化について独自に研究するものではなく、世界中の多くの科学者の協力を得て、原則として査読つきの既存文献に基づき、地球温暖化に関する科学的知見を収集・評価し、科学的な観点から何がどの程度分かっているのかを、政策中立の立場から明らかにし公表することです。IPCCの組織は、議長団の下に、第1作業部会(自然科学的根拠)、第2作業部会(影響、適応、脆弱性)、第3作業部会(緩和策)、並びに温室効果ガスインベントリに関するタスクフォースが置かれています。 Q7 なぜ人為的に排出されたCO2などの温室効果ガスが地球温暖化の原因といえるのですか? A7 IPCCは、3段階の理論展開で地球温暖化の原因を人為的なCO2などの温室効果ガスであると説明しています(「人為起源地球温暖化説」)。まず第1に産業革命以降のCO2が「急激に増えている」という観測結果。第2として、増えたCO2は、炭素同位体比から間違いなく人為的なものであるということ。第3として、CO2の増加を組み込んだシミュレーションによって、現在の気温が再現できるという裏づけによるものです。 Q8 温室効果が最も強い温室効果ガスは、水蒸気ではないのですか? A8 水蒸気は温室効果ガスとして最大の寄与率があります。現在の大気の温室効果は約6割が水蒸気、約3割が二酸化炭素によるものです。現在の「地球が温暖である」ためには水蒸気は重要な役割を果たしています。一方、CO2の増加は「地球が温暖化している」原因であり、温暖化が進行すると考えられています。実際には気温上昇に伴い、自然のしくみによって大気中の水蒸気が増えることにより、さらに温暖化が進むことが予想されます。 また、水蒸気が温暖化にどのように関わっているかについては、まだはっきりとは分かっていないこともあります。水蒸気が増えれば温室効果によって気温が上昇しますが、雲ができることによって気温が下降すると考えられています。また、水蒸気は、大気中に10日程度しかとどまれないのに対して、CO2の大気中の寿命は5年~200年であることから、影響は水蒸気にくらべ著しく長期に渡ります。 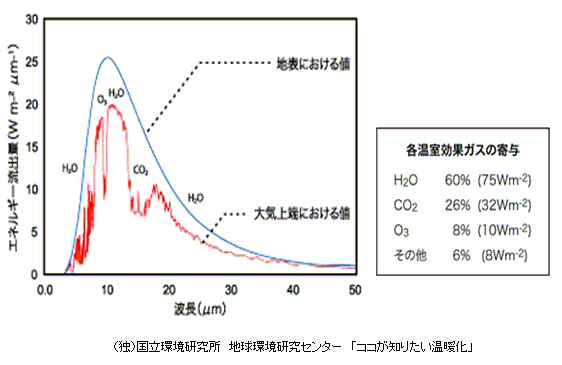 Q9
Q9地球温暖化の将来への影響は、地球全体でどこでも同じですか? A9 地球温暖化の影響は、地域や人々の温度に対する抵抗力などの強さ、生物の種類などによっても異なります。中高緯度地域におけるいくつかの穀物の場合には、2℃程度の気温上昇は、生産力が向上すると予測されていますが、ほとんどの地域や分野において、悪影響が大きくなると予測されています。特に、脆弱な地域や人々に対して、影響はより大きくなると考えられています。例えば、同じ気温の上昇でも、影響は子供や老人に対して強くなります。また、同じ海水面の上昇でも、影響は標高が低いデルタ地帯や島嶼国といった脆弱な地域に大きくなります。 Q10 地球温暖化問題に対する対策として予防原則を用いることが決まったのはいつからですか? A10 地球温暖化問題の対策に予防原則の考え方が用いられたのは、「気候変動枠組条約」からです。気候変動枠組条約は、 大気中の温室効果ガスの濃度の安定化を究極的な目的とし、地球温暖化がもたらす様々な悪影響を防止するための国際的な枠組みを定めた条約です。1992年に開催されたリオの地球サミットにおいて採択され、1994年3月発効しました。条約には5つの原則が定められており、3番目の原則に予防原則が入っています。5つの原則とは、(1)締約国の共通だが差異のある責任に基づく気候系の保護、(2)開発途上締約国等の国別事情の勘案、(3)速やかかつ有効な予防措置の実施、(4)持続的開発を推進する権利と義務、(5)開放的な国際経済システムの確立に向けて推進・協力です。 Q11 地球温暖化問題について、科学者にはどんな対立があるのですか? A11 原因や影響予測評価に不確実性が残っている地球温暖化問題を巡る科学者の対立は、概ね2つの論争として整理できます。一つは、気温上昇に与える雲やエアロゾルなどの影響といった気候変動システムに関する対立、及びシミュレーションによる予測結果やその影響の度合いの評価に関する対立といった自然科学的論争です。もう一つは、現在の地球は、地球温暖化問題以外にも貧困問題、エイズ問題など様々な地球規模の問題を抱えていますが、どの問題に対して優先的に予防原則を適用し、資金や資源を回すべきかという予防原則の適用に関する論争です。いずれの場合においても、こうした問題に関わる科学者や技術者には、情報開示や説明責任が求められているといえます。 Q12 適応策を適用する場合の注意点にはどのようなことがありますか? A12 地球温暖化の影響は、時間・空間的な広がりを持っていますが、その影響を明確に予測することはできません。そのため、具体的な適応策の実施に当たっては、多面的・総合的な検討として、その地域の「脆弱性」を評価することが重要とされています。地域の脆弱性の評価方法は、地域の自然環境、社会環境、並びに適応能力といった情報から、安全面、健康面、経済面、快適さ、文化や歴史といった視点から総合的に評価します。また、緩和策と適応策との関係については、IPCC第4次評価報告書などにおいても、互いに補完し合うことで気候変動によるリスクの低減に寄与することから、バランスのとれた対策の必要性が重要であるといわれています。 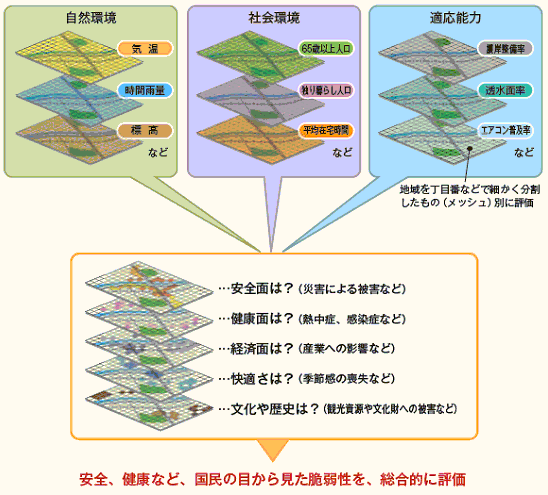 (出典:温暖化から日本を守る適応への挑戦,環境省) Q13 日本では太陽光発電の買取についてどのような制度になっていますか? A13 平成21年11月から「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(平成21年7月1日成立)にもとづいて、住宅用の太陽光発電設備による電気のうち、自家消費した分を差し引いた余りの電気を対象として、電力会社が買い取ることとなりました。買取価格は、太陽光発電設備容量が10kW未満の場合は48円/kwh、太陽光発電設備容量が10kW以上で500kW未満の場合は24円/kwhとなりました。 ■3. 生物多様性■ Q14 生物多様性は生物の種数のことではないのですか? A14 ある地域に生活する生物の種数のことを生物相(Biota)と呼んでいます。日本には約90,000種の生物が生活していると言われ、生物多様性を表現する一つの指標と見ることもできます。生物多様性とは生物相に加え、さらにそれぞれの種がどれくらいの数がいるか、あるいはつながりはどうであるかなどにも踏み込んだ考え方です。 Q15 生物多様性という言葉は、いつ頃から使われているのですか? A15 生物多様性に相当するBiodiversityという言葉は、1985年、アメリカのW.G.ローゼンによって造られたと言われています、Biodiversityという言葉を初めて公式文書に使ったのは、同じくアメリカの生物学者E.O.ウィルソンです。ウィルソンはその著書「Naturalist」の中で、生物多様性の消失は未来の人類に対して取り返しのつかない罪であると述べています。 Q16 生物多様性はどれくらいの速さで低下しているのですか? A16 生物多様性の低下の指標のひとつとして、絶滅種の数が挙げられます。絶滅種数は資料によっても異なりますが、恐竜時代は1年間に0.001種、1万年前には0.01種、1000年前には0.1種、100年前からは1年間に1種の割合で絶滅しているとする試算もあります。そして現在では、1日に約100種、1年に40,000種と、種の絶滅速度は急激に上昇し続けていると言われています。 Q17 生物多様性を数値化することはできるのですか? A17 生物多様性のうち種の多様性を数値化したものとして、種多様度指数というのがあります。種多様度指数は、種の数とそれぞれの個体数から計算されます。代表的なものとしてはSimpsonの多様度指数、Shanon指数などがあります。 Q18 「自然の権利」の考え方は古くからあるのですか? A18 「自然の権利」は、1949年、アメリカのアルド・レオポルドの著書「土地倫理」の中で提示したのが最初とされています。レオポルドによれば、「自然は共同体であり、土地倫理はヒトという種の役割を土地という共同体の征服者から、平凡な一員、一構成員へと変える」と述べ、人間至上主義を強く批判しました。(出典:Wikipedia) ■4. 化学物質と環境リスク■ Q19 四大公害には水俣病のほかに何がありますか? A19 我が国で1950年代後半から1970年代の高度経済成長期に発生した以下の四つの公害を四大公害と呼んでいます。 水俣病(1954年、熊本県水俣湾)、イタイイタイ病(1950年、富山県神通川流域)、新潟水俣病(1963年、新潟県阿賀野川流域)、四日市喘息(1959年、三重県四日市) Q20 「予防原則」は「未然防止」とはどう違うのですか? A20 「予防原則」は、人の健康や環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼす恐れがある場合、科学的に因果関係が十分証明されない状況でも、規制措置を可能にする制度や考え方のことです。これに対し「未然防止」とは、因果関係が科学的に証明されるリスクに関して、被害を避けるために未然に規制などを行なうことであり、両者は意味的に異なると解釈されます。 Q21 「化審法」で規制されている化学物質の種類はどのように管理・公表されていますか? A21 「化審法」(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)に関係する厚生労働省、経済産業省及び環境省が化学物質の安全性情報を広く国民に発信するために「3省共同化学物質データベース(J-CHECK)」が作成されインターネット上で公開されています。 Q22 化学物質を対象とした法律はほかにどのようなものがありますか? A22 主なものとして「化審法」のほかに「化学物質排出把握管理促進法(化管法)」があります。それぞれの役割は以下のとおりです。 「化審法」:主に供給者の観点から対応を求め、新規化学物質等の安全性審査に基づき製造・輸入を規制(蛇口規制)する。 「化管法」:事業者に特定の化学物質の排出量等の届出を義務付け、自主的な化学物質の管理を促進する。 「化管法」は以下の2つの制度を大きな柱としています。 PRTR制度:対象化学物質について、事業所外への排出・移動量を事業者が自ら把握し国に届出ることを義務付ける制度 MSDS制度:対象化学物質又はそれを含む製品を譲渡又は提供する際に、その化学物質の性状及び取り扱いに関する情報(MSDS)を事前に提供することを義務付ける制度 Q23 化学物質の毒性を定量的に把握するにはどのようにするのですか? A23 多くの場合、動物を用いた毒性試験の結果から有害性を推定することが行われます。しかし、すべての種類の有害性についてすべてのデータを集めることは現実的に困難であり、段階的アプローチが用いられています。化審法の新規の生産・輸入登録では、変異原性試験と28日間反復投与毒性試験のデータを基に評価が行われます。そして、よりリスクが大きくなる可能性のあるとき、さらに詳しい試験を、時間と費用をかけて行うことになっています。例えば化審法では、生分解性が悪く魚への濃縮性が大きな化学物質は、種々の長期慢性毒性試験を行うことが要求されます。 ■5. 循環型社会と資源・廃棄物■ Q24 我が国の物質フロー指標はどのように推移しているのでしょうか? A24 物質フロー指標には「資源生産性」、「循環利用率」、「最終処分量」が定められています。 平成2年度に約21万円/tであった「資源生産性」は、平成12年度には約26万円/tに向上し、平成18年度には約35万円/tにまで推移しています。 「循環利用率」は平成2年度には約8%であったものが、平成12年度には約10%に向上し、平成18年度には約12.5%に推移しています。 また、「最終処分量」は平成2年度には約1億1,000万tであったものが、平成12年度には約5,600万tに削減され、平成18年度には約2,800万tにまで削減が図られているものです。それぞれの指標は平成27年度の目標数値として、資源生産性は約42万円/t、循環利用率は約14~15%、最終処分量は約2,300万tに設定されており、この目標に向けて順調に推移している状況にあります。 Q25 昭和30年代の社会と現代の社会が異なる点の本質はどこでしょうか? A25 資源・廃棄物などの分野において、昭和30年代と現代の社会におけるライフスタイルが大きく異なる点の本質は、「利便性や快適さの追求が現代は具現化されている」ことにあり、この結果が現在の物質循環や環境破壊に様々な形となって影響が現れているものです。現代社会で生活を営む我々は利便性や快適さの享受をある程度抑えることはできても、完全に手放すことは難しいといえます。「技術」、「インセンティブを促す制度」、「意識の共有(共通認識)」がこれらを改善に向けて推進するための根幹をなす要素であり、「技術」とそれを扱う技術者は環境倫理を実践することを通じて、循環型社会の形成に向けて大きな役割を担っているものです。 Q26 循環型社会を支える国際条約にはどのようなものがあるのでしょうか? A26 資源有効利用促進法や様々なリサイクル法などの国内法の他に、国際社会においても資源・廃棄物などを通じて循環型社会を構築し、環境保全を推進する様々な国際条約が批准されています。これらには、廃棄物などの海洋投棄を規制する「ロンドン条約」、湖沼の環境保全を通じて野生鳥類などを保護する「ラムサール条約」、有害廃棄物の国際越境移動を規制する「バーゼル条約」、PCBやDDTなどの残留性有機汚染物質の扱いや移動などを規制する「POPs(Persistent Organic Pollutants)条約」などがあります。また、広義には2005年に発効した「気候変動に関する国際連合枠組条約(地球温暖化防止条約)」なども循環型社会を支える国際条約の範疇に入るものといえます。 Q27 現在、廃棄物発電で回収されている電力はどれ位でしょうか? A27 我が国の2003年現在における廃棄物発電施設が備える発電出力は、一般廃棄物で約135万kW、産業廃棄物で約20万kWの合計約155万kWの能力を有しています。 また、年間発電電力量の実績は一般廃棄物で約69億kWh、産業廃棄物で約15億kWhの合計約84億kWhとなっています。これは、一般的な家庭が年間5,500kWhの電力を消費したと仮定した場合、約153万世帯の家庭が1年間に消費する電力を廃棄物が賄っていることに相当します。 Q28 インセンティブを促す制度とはどのような制度をいうのでしょうか? A28 インセンティブ(incentive)とは、「誘引」、「目標を達成するための刺激」、「やる気を起こさせるような刺激」などの意味があります。 制度は本来他律的なものですが、環境倫理のもとに資源や廃棄物を通じて循環型社会の形成を推進するために策定される制度は、行動の自発を促すものでなければなりません。そのためにはその制度を遵守することを通じて、自らが社会に貢献していることの充実感を得たり、何らかの形で更なる制度の拡充に繋がることを目的とした利益を得るシステムであることがこの制度の望ましい形といえます。空缶の返却に伴い料金が払い戻されるデポジット制などはこの代表的な例の一つといえます。 ■6. 低炭素社会とエネルギー■ Q29 日本は化石エネルギーにどの程度依存しているのですか? A29 一次エネルギー(資源等をエネルギーとして直接利用する場合)は、一般に石油、石炭、天然ガス、原子力、水力、新エネルギー・地熱に区分され、これらのうち、石油、石炭、天然ガスが化石エネルギーに該当します。一次エネルギー消費量全体に占める化石エネルギーのシェアは、オイルショックを経験した1970年代には90%を超えていました。2007年には化石エネルギーのシェアは約84%に減っていますが、消費量自体は増加しています。 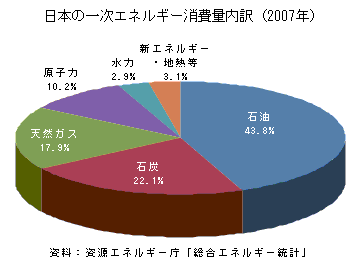 Q30
Q30森林等を耕作地に変えてエネルギー作物を栽培している具体例はありますか? A30 バイオマスエネルギーは再生可能エネルギーの一つであり、自然界の動植物に由来しているため、自然環境にも優しいエネルギーといえます。しかしながら、ブラジルのアマゾンなどではメタノールの原料となるトウモロコシを栽培するために、熱帯雨林の伐採・耕作地利用が進みました。このような開発が行われると、豊かな生態系は破壊され、熱帯雨林が持つCO2吸収機能も失われてしまいます。 Q31 再生可能エネルギーには太陽光発電や風力発電のほかに何がありますか? A31 再生可能エネルギーには、自然エネルギーとリサイクルエネルギーの2つがあります。太陽光、風力以外の自然エネルギーとして、発電の場合は水力、地熱、波力、海洋温度差などが利用されます。また、熱として利用する場合は、太陽熱、雪氷熱(冷熱)が代表的です。リサイクルエネルギーには、廃棄物発電や廃棄物熱利用、廃棄物燃料、廃熱利用などがあります。これらに加えて、木質廃材、稲わら、家畜ふん尿などのバイオマスもエネルギーとして利用されています。 Q32 省エネや再生可能エネルギーの普及にはどのように取り組めばよいですか? A32 省エネや再生可能エネルギーの利用には専用の機器が必要であり、その際の費用負担が問題となる場合が多いため、経済性の面から導入しやすい環境を整えることが重要です。太陽光発電システムを例にあげると、一般家庭で設置する場合には費用の一部が助成されます。また、発電した電力を地域の電力会社が買い取るよう制度化されています。 Q33 低炭素社会の具体的な実現イメージについて教えてください。 A33 低炭素社会は「CO2排出量を削減しつつ、人々のニーズを満たす社会」ですが、実現の方向性は地域特性によって様々です。たとえば、たくさんの人々が暮らし、産業の集積や交通基盤の整備が進んだ都市では、生活、事業活動、移動などに大量のエネルギーを必要とします。このため、エネルギーを効率よく使う技術を導入するとともに、機能性の高いインフラとして整備することによって、便利さと快適さを維持しつつ、地域に最適なエネルギー利用を図り、エネルギー消費量を今よりも少なくなくすることが低炭素社会の実現イメージとなります。 ■7. 環境コミュニケーション■ Q34 実際に、どのような方法で環境コミュニケーションが行われているのですか? A34 環境情報には発信主体と受信主体があり、その間に仲介者が入る場合もあります。 情報の送り手や受け手には、個人、企業、NPO・NGO、行政などの様々な主体が、仲介者には、主にNPO・NGOや研究機関、マスメディアなどがなり得ます。 環境情報の媒体としては、従来は新聞や雑誌のような印刷媒体をはじめラジオやテレビのような電波媒体を利用したマス媒体(広告)が主流でしたが、環境報告書やCSRレポートなどの配布物に加え、インターネットなどの電子媒体により、タイムリーで細やかな環境情報の発信が可能となっています。 近年では、企業の広告、製品ラベル、パッケージ、環境/CSRレポートなどを通じて、製品や自社の環境配慮への取り組みなどを、環境情報として発信する企業活動として定着しつつあります。 Q35 専門家と住民が情報を共有するため、どのような機会があるのですか? A35 【環境アセスメント】 環境アセスメントでは、文章形式と会議形式のコミュニケーション手法がとられます。文章方式では、事業者の側から方法書、準備書、評価書、見解書が作成され、市役所などに縦覧され、住民がこれらの文章を読むための場が設定されます。住民側は、これに対して意見書を出すという形で意見をします。一方会議形式には、説明会と公聴会があり、文章形式に比べ、直接的なコミュニケーションが行われています。 【ワークショップ】 直接的な環境コミュニケーションの手法として、近年、住民参加型まちづくりや公園づくり、環境保全における合意形成の手法として、ワークショップ手法が用いられることが多くなっています。ワークショップではファシリテーターと呼ばれる司会進行役の人が、参加者が自発的に作業をする環境を整え、参加者全員が体験するものとして運営されます。 ワークショップの効果として期待されているものとして、参加者同士の体験共有、意見表出(ブレインストーミング)、創造表現、意見集約その他のコミュニケーションを深めることがあり、地方自治分野では市民間の合意形成のスタイルとしても注目されつつあります。 Q36 分かりやすく伝えるとは、具体的にどのようなことをすればいいのですか? A36 技術者は、所属するコミュニティ(学協会、業界など)において、「技術」や「製品」などに関する情報を正確に表現し、議論を進めやすくするために専門用語を用います。専門用語は、同じコミュニティに所属する技術者同士にとって誤解なく議論するために有効です。しかし、技術者のコミュニティに属さない公衆(一般市民や消費者)は、技術者が用いる専門用語を正確に理解することは困難となります。 一方、日常用語とは、通常の生活において公衆(一般市民や消費者)が日常的に使う言葉のことです。 技術者と公衆との双方向のコミュニケーションでは、技術者から公衆に向けての情報提供に際して、技術内容に関する「正確さ」と「わかりやすさ」をバランスさせる必要があり、その方策として、専門用語を、比喩などを使ってわかりやすい日常用語に変換する必要があります。 このほか、 ・簡潔な文章と文体を心がける。 ・文章に加え、表、グラフや写真、イラストなどを交えて表現する。 ・表やグラフなど数値等の意味を適切に説明する。 ・専門用語は可能な限り避け、場合により注釈を付ける。 などの配慮が必要です。 Q37 実際にどのような環境教育が行われているのですか? A37 【環境教育の主な範囲】 環境教育の範囲は、大きく4つに分けることができます。 (1)自然環境系:地域の自然に関わる環境教育 (2)生活環境系:地域の社会に関わる環境教育 (3)地球系:地球規模の自然と社会に関わる環境教育 (4)総合系:自然系、生活系、地球環境教育系が、持続可能な地域づくり 【環境教育の実施方法】 環境教育の実施方法は多岐にわたりますが、大きく5つに分けることができます。 (1)学習活動: 自然や環境について学ぶ活動。「樹木の冬芽の観察」、「田んぼの生き物調査」など自然そのものについての学習や「資源マップ作成」、「古地図調べ」など身近な生活環境、環境問題を学ぶ活動。 (2)生活体験活動: 衣食住などの生活体験活動。「農作業の体験」、「野草茶作り」、「雑木林の手入れ体験」、「原始的な方法で火をおこす」、「廃油の石鹸作り」など。自然を利用した生活技術や自然と調和した生活体験活動。 (3)創作活動: 自然を素材とした創作活動や芸術的活動。「間伐材を利用した木工・竹細工」、「落ち葉の絵本作り」、「自然素材で製作した楽器で音楽を楽しむ」、「森の中での歌(俳句)作り」など。 (4)スポーツ活動: 野外での身体活動。「ツリークライミング」や「ウオーキング」などのスポーツを、自然や環境と関わりを持つ活動と位置づけ、からだで自然を感じる活動。 (5)感受体験活動: 「見る・聞く・嗅ぐ・味わう・触る」という五感を使って周囲の自然に「気づく」という体験をする。「ナイトハイク(夜の暗さや静寂を体験する)」などの活動。 【参考文献】日本環境教育フォーラム編著「日本型環境教育の提案」(1994年・改定版2000年)小学館 Q38 地球温暖化問題では、どのような利害関係が生じるのですか? A38 【地球温暖化は、先進国と途上国の格差を拡大する 】 日本やアメリカ、カナダ、ヨーロッパ、ロシアなどの先進国では、気温の上昇幅が小さければ悪影響だけでなく、冬季の暖房費用の軽減など好影響になる可能性もあります。また悪影響に対処するだけの技術力も資金力も有しています。 一方、少しの気温の上昇で多くの途上国が経済的損失を被り、温暖化が進行すればするほど損害も大きくなります。しかし途上国にはその悪影響に備えるだけの技術力の資金力もありません。 その結果、地球温暖化の利益を受ける人がいても、地球全体では被害を被る人の方が多くなると予測されています。 【海面上昇の影響は、脆弱な国ほど大きくなる】 2080年代までに海面水位が40cmしか上昇しなかった場合でも、海面上昇がない場合に比べて、毎年高潮により浸水を受ける人口が世界全体で7500万~2億人も増加すると予測されています。 また、熱帯、亜熱帯の島嶼国は、標高の低い土地が多いのに加えて経済的に貧しい人々が多く、もっとも深刻な影響を受けやすいと考えられています。海面の上昇によって、沿岸侵食の拡大、土地や財産の損失、人々の移住、高潮のリスクの増大、沿岸の自然生態系の減衰、淡水資源への塩水(海水)の浸入が起こり、これらの変化に対処するため高いコストが生じると推測されます。 また観光は多くの島にとって収入及び外貨獲得の重要な源だが、異常気象の増加などや海面水位の上昇から深刻な観光資源の損失に見舞われると予測されています。 【参考文献】「全国地球温暖化防止活動推進センターホームページより (http://www.jccca.org/) |