|
Q1-01.最近、知的財産高等裁判所(知財高裁)という名前を耳にすることがありますが、どのような裁判所なのですか? Q1-02.国家の知的財産戦略における「第2期」の取り組みとしては具体的にどのようなものがあるのですか? Q1-03.よく著作物に©マークが表示されているのを見かけるのですが、©マークを付けないと我が国での保護を受けられないのでしょうか? Q1-04.「参入障壁」には、知的財産権以外にどのようなものがあるのか教えてください。 Q1-05.問題になりそうな他社特許が見つかった場合、どのような結論が得られれば“問題なし”と判断してよいのですか? Q1-06.公開公報ベースで調査したら、自社にとって問題となりそうな他社の公開公報が見つかりました。未だ特許されていない出願中の案件のリスクを現時点で判断することは難しいと聞いたのですが本当ですか? Q2-01.そもそも、なぜ技術経営力が重要なのですか? Q2-02.知的財産の活用を図るためには、知的財産の価値評価が必要になってくると思うのですが、この価値評価はどのようにして行うのですか? Q2-03.自社にとっての新規事業は、事業ポートフォリオのどのセグメントに分類されるのですか? Q2-04.製品ライフサイクルには例外はないのですか? Q2-05.特許群の管理の具体的なイメージが湧きません。何か具体例を挙げて説明してください。 Q3-01.基本技術の周辺固めのために知的財産情報を活用している企業の具体的なケースを紹介してください。 Q3-02.用途技術の創造のために知的財産情報を活用している企業の具体的なケースを紹介してください。 Q3-03.更なる研究開発の方向性の決定のために知的財産情報を活用している企業の具体的なケースを紹介してください。 Q3-04.製品クリアランス調査は、具体的にどのようにして行えばよいのですか? Q3-05.知的財産情報は全て秘密情報として取り扱うべきなのですか? Q4-01.このケースで問題となる進歩性および先願の関係についてもう少し詳しく教えてください。 Q4-02.国内優先権が利用できる時期的な要件は何ですか? Q4-03.早期審査は、どのような出願であっても利用できるのですか? Q4-04.発明者が審査官との面接を希望する場合にはどうしたらいいですか? Q4-05.日本の特許出願をベースに外国特許出願する場合、どのようなルートがあるのですか? Q5-01.ここに示された活用形態のいずれにも該当しない場合、知的財産権が活用されていないということになるのでしょうか? Q5-02.「囲い込み戦略」をとっている事業分野に他社が参入してきた場合、これを排除するための法的手段にはどのようなものがありますか? Q5-03.クロスライセンスにおける当事者間の力関係はどのようにして決まるのですか? Q5-04.標準技術に関するパテントをプールしている組織からライセンスを受ければ、その技術に関する他社特許侵害リスクは0と考えてよいのですか? Q5-05.オープンソースおよび知的財産権の仕組みをうまく利用している具体的なケースを教えてください。 Q6-01.発明の発掘は、具体的にどのようなアプローチで行ったらよいですか? Q6-02.発明提案書の提出に関する発明者へのインセンティブにはどのようなものがありますか? Q6-03.ブラッシュアップ会議で注意すべきことはありますか? Q6-04.特許出願したものは全て特許庁で審査されるのではないのですか? Q6-05.商品ラベルに特許番号ではなく特許出願番号を表記しているケースを見かけたのですが、特許出願番号の表記にどのような意義があるのでしょうか? Q1-01 最近、知的財産高等裁判所(知財高裁)という名前を耳にすることがありますが、どのような裁判所なのですか? A1-01 日本国内の知的財産権を巡る係争に関して司法判断を下す専門の裁判所で、東京高等裁判所の「特別の支部」に相当します。 小泉政権の諮問機関である知的財産推進会議などで、増え続ける知財関連の係争を専門的かつ迅速に処理するために、専門裁判所の必要性が議論されました。この議論を経て、2004年6月に「知的財産高等裁判所設置法」が成立し、その後の準備期間を経て2005年4月1日に発足したのが知的財産高等裁判所(略して知財高裁)です。 知財高裁が取り扱う事件には、 (1)特許庁が行った審決(審査の上級審である審判における判断)に対する不服申立てに相当する審決取消訴訟のすべて (2)特許権や実用新案権といった技術型の民事控訴事件のすべて (3)意匠権や商標権といった非技術型の民事控訴事件の一部(東京高裁の管轄事件のみ) 等があります。 Q1-02 国家の知的財産戦略における「第2期」の取り組みとしては具体的にどのようなものがあるのですか? A1-02 第2期の施策を定めた「知的財産推進計画2006」では、知的創造サイクルにおける創造を特に重視し、次のような観点の施策が多数盛り込まれています。 ●7つの重点事項 1.国際的な展開 2.地域への展開および中小・ベンチャー企業の支援 3.大学などにおける知財の創造と産学連携の推進 4.出願構造改革・特許審査の迅速化 5.コンテンツの振興 6.日本ブランドの振興 7.知財人材の育成 ●5つの視点 ・イノベーションを促進する ・知的財産文化を国内志向から国際志向に変える ・スピードある改革を行う ・知的財産とそれ以外の価値とのバランスに留意する ・総合的な取り組みを行う Q1-03 よく著作物に©マークが表示されているのを見かけるのですが、©マークを付けないと我が国での保護を受けられないのでしょうか? A1-03 著作物に対する©マークの表示は、日本の著作権法で保護を受けるために必要な要件ではありません。したがって、©マークを付けなくても、著作権法による保護を受けることができます。それにも関わらず©マークを付しているのは、著作物の国際的な保護を図るといった理由によるものです。 Q1-04 「参入障壁」には、知的財産権以外にどのようなものがあるのか教えてください。 A1-04 参入障壁とは、ある業界に新規参入しようとする会社にとって参入を妨げる障害のことをいいますが、具体的な参入阻止要因には、企業が備える優位性と、法規制等があります。前者の優位性は、規模の経済性、ブランド力、技術力、スイッチング・コストの高さなどを含みます。また、後者の法規制については、例えば、レッスン6の「ヘルシア緑茶」の知的財産戦略で紹介しているように、特定保健用商品の許可が挙げられます。 参入障壁の高さは、新規参入の脅威を測る上での指標になります。「競争の戦略」の著者であるマイケル・ポーター(Porter,M.E.)は、参入障壁の規模を測る具体的な指標として以下の8つを挙げています。 ・規模の経済性が働くか ・製品の差別化が存在するか ・巨額の投資が必要か ・仕入れ先を変更するコストは大きいか? ・流通チャネルの確保は難しいか? ・規模の経済性以外のコスト面での不利な点が存在するか? ・政府の政策による参入の制限や規制が存在するか? ・参入に対し強い報復が予想されるか? Q1-05 問題になりそうな他社特許が見つかった場合、どのような結論が得られれば“問題なし”と判断してよいのですか? A1-05 “問題なし”と判断してよいケースには、以下の(1)~(5)があります。 (1)現時点で権利が存在しない 権利存続期間の満了による消滅、年金未納による消滅、無効審決の確定による遡及消滅等があります。現時点における権利の状態は、特許原簿等で確認することができます。 (2)対象製品がクレームに抵触しない(抵触性) クレームの解釈では、審査経過で主張された事項も重要になります。また、クレーム文言上の抵触のみならず、均等論上の抵触についても考慮する必要があります。 (3)先行技術の存在によってクレームが無効(有効性) その特許の出願前のものでなければ先行技術(無効資料)にはならない点に注意が必要です。 (4)先使用による通常実施権 その特許の出願前に実施または実施の準備をしていた場合、一定要件下で特許非侵害の法的地位が認められています。 (5)その他 その特許を実施する正当な権原を有する者から購入している場合等 Q1-06 公開公報ベースで調査したら、自社にとって問題となりそうな他社の公開公報が見つかりました。未だ特許されていない出願中の案件のリスクを現時点で判断することは難しいと聞いたのですが本当ですか? A1-06 確かに、既に特許されている案件と比較すれば難しいのは事実です。特許庁での審査過程において、どのような方向で権利化されるのかわからないという不確実な要素があるからです。しかしながら、この不確実な要素を予測できれば、出願中のものであってもある程度のリスク判断が可能です。そのためには、以下のプロセス(1)~(3)が欠かせません。 (1)その出願案件の出願時点における技術水準の把握 (2)その出願案件のクレームおよび明細書全体の記載事項に基づいた、特許になりそうなネタの抽出 (3)(1)の技術水準に基づいた、抽出されたネタの特許可能性の予測 上記プロセスをキチンと行うことは大変な部分もありますが、出願中の案件についても侵害リスクを判断しなければならないというケースは今後増えてくるかもしれません。 Q2-01 そもそも、なぜ技術経営力が重要なのですか? A2-01 我が国の国際競争力を回復するために有効な手段と考えられているからです。 技術立国を指向する我が国にとって、国際競争力の低下は近年重大な問題となっています。 我が国の技術・研究開発人材の水準および知的財産権の水準は共に高いレベルにある反面、マネジメントの水準は他国に大きく水を空けられています。また、1990年代に日本の製造業が研究開発投資も行い技術力も十分あると思えるのに収益が落ち込み、結果的に、米国企業と大きく差がついてしまったという経緯もあります。これらのことから、我が国には、科学技術や知的財産を経済活動に結びつける力、すなわち技術経営力が不足しているとの認識に至り、これを向上させようという考え方が重視されるようになりました。 Q2-02 知的財産の活用を図るためには、知的財産の価値評価が必要になってくると思うのですが、この価値評価はどのようにして行うのですか? A2-02 価値評価の手法については様々な研究が行われていますが、決定打が未だ確立されていないのが現状です。 知的財産の価値は、技術の市場性、技術革新、法律問題(権利範囲の解釈や特許の有効性)といった知的財産固有の要素を評価した上で行わなければなりません。しかしながら、これらの要素は不安定な部分が多く、定量的な評価が難しいのです。 一般に、財産の評価を行う際のアプローチは、(1)取得に要したコストを基準に価値を評価するコストアプローチ、(2)市場価格や類似の売買事例を基準に価値を評価するマーケットアプローチ、(3)試算が生み出す収益等から価値を評価するインカムアプローチに大別されます。個別性が高い知的財産は、インカムアプローチが適しているといわれていますが、それでさえ、知的財産による収益の算出方法や収益に対する知的財産の寄与度などの問題があります。 Q2-03 自社にとっての新規事業は、事業ポートフォリオのどのセグメントに分類されるのですか? A2-03 新規事業には、主として以下の3つのパターンがあります。 (1)ハード要素(技術的な革新や独自性)で事業展開を図るパターン (2)ソフト要素(マーケティング手法やビジネスシステムの改革)で事業展開を図るパターン (3)新規なニッチ市場の開拓 多くの場合、市場成長率が高いがゆえに新規参入の意欲が働き、また、その参入時点での相対マーケットシェアは低いものと考えられます。したがって、新規事業の多くは“問題児”に属するものと思われます。 なお、過当競争を経て市場成長率が鈍化した状態で、最もコスト・パフォーマンスの高い製品を新規に投入するといった形態も新規事業として考えられます。この場合には、形式的には“負け犬”に分類されることになります。しかしながら、コスト・パフォーマンスの高い製品を作るための優れた生産技術等が存在するならば、実質的には、やはり“問題児”と同様の取扱いが必要になるものと思われます。 Q2-04 製品ライフサイクルには例外はないのですか? A2-04 ある製品のライフサイクルの途中で、イノベーションによって新たな製品ライフサイクルが生じることはあります。レッスン6で紹介する「NAND型フラッシュメモリ」は、その典型例です。元々は汎用ROMの一種に過ぎませんでしたが、現在では、汎用ROMとは異なる独立した市場を形成するに至っています。 Q2-05 特許群の管理の具体的なイメージが湧きません。何か具体例を挙げて説明してください。 A2-05 図は、ある製品における個々の自社特許の位置付けを可視化した特許マップの一例を示しています。このような特許マップを作成することによって、それぞれの特許が製品のどの機能や構成をカバーしているのか容易に把握することができます。分類カテゴリーを設定する際は、機能、構成あるいは要素技術等に着目するとよいでしょう。なお、この特許マップをルートとして、より詳細な情報を紐付けているケースも良く見受けられます。 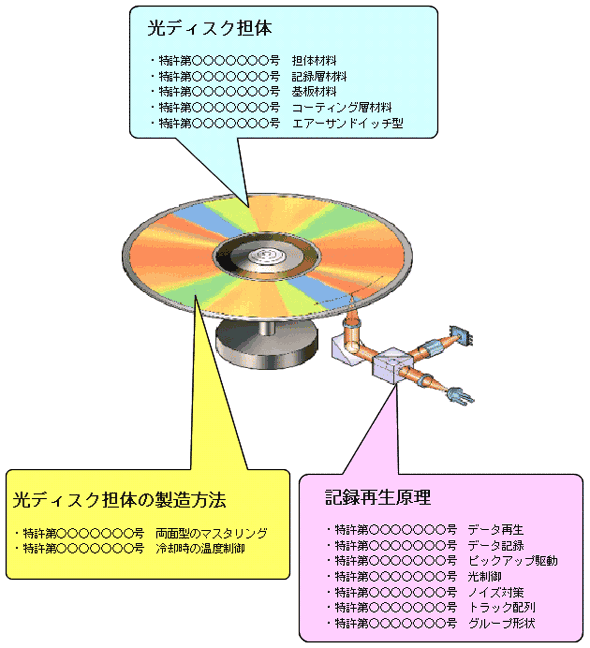 Q3-01
Q3-01基本技術の周辺固めのために知的財産情報を活用している企業の具体的なケースを紹介してください。 A3-01 化学分野の製品が中心であるA社は、他社へライセンス供与せずに独占を享受する戦略が会社の収益を増大させる最善の戦略であると考えています。そして、特許によって効果的に事業を独占するためには、単独の特許によって独占しようとするのではなく、特許群を形成する戦略が効果的であるとも考えています。かりに、他社にライセンス供与するとしても、その効果的な特許群をパッケージで取り扱う方が付加価値が高く、高いロイヤルティでライセンス供与をすることができるからです。 一つの有力な発明をして特許権を取得すると、他社は、これを回避して代替技術を開発しようと周辺へ逃げようとします。そこで、A社は、「自分が他社の技術者だったらどこを研究して、代替技術を開発しようとするか?」という命題に基づいて、権利化しておきたい部分を浮かび上がらせて、そこを重点的に研究開発することによって、有力な特許群を構築するようにしています。 引用文献 経済産業省 特許庁 『戦略的な知的財産管理に向けて -技術経営力を高めるために-<知財戦略事例集>』、2007年。 Q3-02 用途技術の創造のために知的財産情報を活用している企業の具体的なケースを紹介してください。 A3-02 B社は、中間製品の製造・販売を事業の主軸としており、主な研究開発の対象は「中間製品自体」および「その製造方法」です。B社は、特許が取得できるような「中間製品自体」や「その製造方法」に関する発明を創造した場合には、更なる開発対象として、(1)中間製品を利用した最終発明(いわゆる「用途発明」など)、(2)中間製品を最終製品にするための配合剤、(3)中間製品から最終製品を製造する方法、(4)中間製品から最終製品を製造する装置など、下流事業に関する全ての段階の技術を含ませるように対応しています。 これにより、最終製品を製造するユーザ企業は、中間製品の特許が切れた後も、最終製品に関する特許が生きている間は、その中間製品をB社から購入せざるを得ない状況を維持でき、B社の製品シェアを確保することが可能になります。そのためには、B社の中間製品に関する発明が創造された後は、その製品をユーザに提供する前に先行して用途発明の開発を進めて、ユーザよりも先に権利を押さえていくことが重要になります。 また、反対に、用途も含めて特許を取得しないと、仮に中間製品の納入先の企業CがB社の中間製品を用いた用途発明特許を取得した場合に、B社は、企業C以外のユーザ企業に対して、その用途発明に用いるための中間製品を納入することができなくなり、事業としては非常に問題となってしまいます。つまり、企業C以外は、B社の製品を購入する意味がなくなってしまうわけです。 このように、中間製品に用途の知的財産を負荷して販売するのが、B社の事業戦略でもあります。 引用文献 経済産業省 特許庁 『戦略的な知的財産管理に向けて -技術経営力を高めるために-<知財戦略事例集>』、2007年。 Q3-03 更なる研究開発の方向性の決定のために知的財産情報を活用している企業の具体的なケースを紹介してください。 A3-03 D社は、ある商品に関する研究開発に先立ち、事業部からの要請に基づき特許マップを作成しました。そのマップは、技術に対応する「基本特許」、「自社特許及びその契約状況(利用可能性)」、「競業他社の特許取得・出願状況」、「自社における試行実績と結果」、「その技術の利点」、「その技術の欠点」を整理したものです。D社は、特許マップを俯瞰することによって、技術的に有用と思われる分野に、特許群の隙間があることに気がつきました。そこで、その技術分野の開発に着手し、その開発成果物は、後に量産化までこぎ着けることができました。 引用文献 経済産業省 特許庁 『戦略的な知的財産管理に向けて -技術経営力を高めるために-<知財戦略事例集>』、2007年。 Q3-04 製品クリアランス調査は、具体的にどのようにして行えばよいのですか? A3-04 決まった手法が存在する訳ではありませんが、一例をご紹介します。この手法は、多数の特許が込み入って存在する電気・機械の分野で良く用いられます。 (ステップ1)調査対象の特定 まず、調査対象となる製品のどの機能・構成について調査するのかを特定します。 (ステップ2)検索式の設定 つぎに、特定された調査対象に基づいて、類似語や同義語に配慮しながら、検索式を設定します。 (ステップ3)機械検索の実行・抄録の取得 検索式に基づいて機械検索を実行し、ヒットした案件の抄録(発明の課題および構成を簡潔にまとめたもの)を取得します。ヒット件数が多すぎる場合には、ステップ2に戻って、検索式を見直します。 (ステップ4)抄録ベースでの選別 取得した抄録を読んで、関係ありそうなものを抽出します。 (ステップ5)全文明細書ベースでの選別 関係ありそうなものとして抽出された案件について全文明細書を取得して内容を精査します。これにより、問題特許が存在するか否かを判断することができます。なお、このステップ5で抽出された問題特許については、審査経過書類に基づいて更に詳しく検討する必要があります。 Q3-05 知的財産情報は全て秘密情報として取り扱うべきなのですか? A3-05 情報の性質によって異なります。 一般に、他社特許について検討した資料、自社技術の抵触性をまとめた資料、他社との交渉・ライセンス関連資料等は、秘密情報の度合いが高いといえます。逆に、単なる自他社の公開公報・特許公報それ自体は、秘密とする必要はありません。ただし、これらの公報でも、ある目的(例えば、自社にとっての要注意特許)の下で選別したもの(そのリストを含む)は、秘密情報として管理する必要が生じます。 Q4-01 このケースで問題となる進歩性および先願の関係についてもう少し詳しく教えてください。 A4-01 進歩性とは、いわゆる当業者が出願前の公知文献等から出願に係る発明を容易に考え出すことができない程度の困難性をいいます(特許法第29条第2項)。ここで注意すべきは、進歩性判断のベースとなる公知文献(公開公報を含む)は、出願前に公知になっていなければならず、出願後に公知になったものは該当しないという点です。本ケースで例えば出願A,Bに着目した場合、出願Aは、その出願日から1年6月経過後でなければ出願公開されず、それまでの間は秘密の状態にあります。したがって、出願Aが出願公開されるまでの間に出願Bを出願した場合、出願Bの進歩性の判断に関して、出願Aとの関係は問われないということになるわけです。 一方、先願とは、同一の発明(クレームに記載された発明)について二以上の出願が競合した場合、最先の出願人のみ特許を付与することをいいます(特許法第39条、第29条の2)。先願は、進歩性のように文献の公知性を問うことなく、単純に出願の前後関係のみに着目して適用されます。また、39条の場合は同一の出願人であったとしても問われます。ただし、39条の場合は出願A,Bのクレームが同一でなければ、第29条の2の場合は明細書記載の発明が同じでなければ、先後願の関係は問われません。 Q4-02 国内優先権が利用できる時期的な要件は何ですか? A4-02 先の出願の日から1年以内です。それ以降は、新規内容の追加は一切認められていない点に注意してください。なお、国内優先権を利用した出願は、先の出願とは別個の出願なので、たとえ先の出願について既に審査請求をしている場合であっても、審査請求も新たにする必要があります。 Q4-03 早期審査は、どのような出願であっても利用できるのですか? A4-03 以下のいずれか1つの条件を満たしていることが必要です。 (1)中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願であること (2)外国関連出願であること (3)実施関連出願であること なお、(3)の「実施関連出願」とは、出願人自身又は出願人からその出願に係る発明について実施許諾を受けた者が、その発明を実施している特許出願をいいます。 Q4-04 発明者が審査官との面接を希望する場合にはどうしたらいいですか? A4-04 まずは、知的財産部の担当者または代理人になっている弁理士に相談しましょう。 なお、面接ガイドラインによれば、代理人(弁理士)が選任されている場合には、原則として代理人が出席することになっており、発明者はこれに同席することができる、と記載されています。発明者は、技術内容を最も詳しく承知している者ですから、面接に同席して直接的に審査官と意思疎通を図ることができます。また、代理人が選任されていない場合には、出願人本人、又は出願人本人以外の責任ある応対をなし得る知財部員等と面接を行う、とあり、この場合、出願人側の応対者において発明者が出席することを妨げるものではない、と記載されています。 Q4-05 日本の特許出願をベースに外国特許出願する場合、どのようなルートがあるのですか? A4-05 パリ条約の優先権を主張して各国に直接出願するルートと、PCT(特許協力条約)を利用するルートとがあります。前者のパリルートの場合、保護を希望する国のそれぞれに対して、その国の書式や言語にしたがった書類を、日本の出願日から12ヶ月以内に個別に提出しなければなりません。一方、後者のPCTルートの場合、日本の特許庁等の受理官庁に特許出願することによって、PCT加盟国に出願したのと同様の効果を得ることができます。ただし、あくまで出願手続を統一するための制度なので、所定の期間のうちに保護を希望する各加盟国での国内手続を進める必要があります。PCTルートを利用するメリットは、翻訳文等を提出して各加盟国の国内手続を進めるまでに30ヶ月の猶予期間が得られる点、および、関連する先行技術文献が記載された国際調査報告を受け取れる点です。 Q5-01 ここに示された活用形態のいずれにも該当しない場合、知的財産権が活用されていないということになるのでしょうか? A5-01 そうとはいいきれません。それが戦略的活用であるかどうかは別の問題として、権利者の目に見えないところで事業に貢献しているケースもあるからです。例えば、A社の特許を競業他社であるB社が問題視し、その特許の検討に時間を費やしてしまった結果、B社の製品出荷が遅れたとします。この場合、B社の事業を遅らせることができたA社の特許は、結果的にA社の事業利益に貢献したといえます(遅れた分だけA社の優位性が維持できたから)。 Q5-02 「囲い込み戦略」をとっている事業分野に他社が参入してきた場合、これを排除するための法的手段にはどのようなものがありますか? A5-02 特許法第100条に規定されている差止請求権があります。“差止請求権”とは、自己の特許権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求する権利です。特許権者は、この権利に基づいて、侵害品の製造・販売などの停止や、侵害品を製造するための設備の廃棄を侵害者に請求することができます。 Q5-03 クロスライセンスにおける当事者間の力関係はどのようにして決まるのですか? A5-03 一つの考え方として、特許力と、製品のボリューム(売上高)とに基づいて、力関係を決定する方法があります。 (ケース1) (A社の特許力)/(A社のボリューム)>(B社の特許力)/(B社のボリューム) →A社の方がB社よりも強い立場 (ケース2) (A社の特許力)/(A社のボリューム)<(B社の特許力)/(B社のボリューム) →B社の方がA社よりも強い立場 (ケース3) (A社の特許力)/(A社のボリューム)≒(B社の特許力)/(B社のボリューム) →A社およびB社は同等の立場 Q5-04 標準技術に関するパテントをプールしている組織からライセンスを受ければ、その技術に関する他社特許侵害リスクは0と考えてよいのですか? A5-04 残念ながらそうはいきません。プールされているパテントに関する侵害リスクは解消されますが、パテントプールに参加している者以外が保有するパテントについては、侵害リスクが残っているからです。 Q5-05 オープンソースおよび知的財産権の仕組みをうまく利用している具体的なケースを教えてください。 A5-05 ある企業では、オープンソースのコミュニティを守るための盾として特許を活用しています。この企業は、オープンソースのコミュニティへの参画を促すために、これに参画する企業に対しては、自社の特許権の使用に対する法的責任を追及しないことを宣言しています。一方で、その特許権を使用して商用化する企業に対しては、ライセンス契約の締結を求めています。 引用文献 経済産業省 特許庁 『戦略的な知的財産管理に向けて -技術経営力を高めるために-<知財戦略事例集>』、2007年。 Q6-01 発明の発掘は、具体的にどのようなアプローチで行ったらよいですか? A6-01 ここでは、新製品に内在する発明を発掘するアプローチの一例をご紹介します。このアプローチは、以下のような手順で行います。 (ステップ1)新製品の変更点・追加点の洗い出し 従来製品で採用されている技術は既に特許性を失っているため、潜在的な発明は、今回の新製品で変更・追加されたものに限定されます。このステップでは、技術内容にあまり深入りせず、例えば機能等に着目して、新製品の変更点・追加点を広い見地で俯瞰します。 (ステップ2)具体的な手段・構造の抽出 上記ステップ1で洗い出された変更点・追加点に関して、具体的にどのような手段・構成で実現しているかを個別に検証します。 (ステップ3)抽出された手段・構造の評価 上記ステップ2で抽出された具体的な手段・構造が特許性を有するか否かを検証します。 ここで注意すべきは、ステップ3における特許性(特に進歩性)の判断です。往々にして技術者は、特許実務上要求されるレベルよりも厳しいレベルで進歩性を判断してしまいがちです。これでは、価値ある発明が埋もれることになりかねません。また、一見、特許性が厳しく思える発明も、製品固有の下位概念に限定することで、特許性が見出せることもあります。 Q6-02 発明提案書の提出に関する発明者へのインセンティブにはどのようなものがありますか? A6-02 まず、職務発明規定の整備による報奨金の充実が挙げられますが、それ以外に、社内表彰、昇進、研究開発環境の充実化等もあります。また、本質論として、「発明提案書の作成・提出も業務の一環である」という社内風土を育んでいくことも重要です。 Q6-03 ブラッシュアップ会議で注意すべきことはありますか? A6-03 ブラッシュアップ会議は仕組みに過ぎず、これを構築しさえすれば成果が出るものではありません。「価値ある特許に育て上げる」という共通の目的の下で、それぞれの参加者が、知恵を出し合わなければ意味がありません。したがって、ある参加者の意見を単に追認するだけの会議や、事前の準備なしにその場で発明の内容を聞いて議論するような会議に陥るのは避けるべきです。 Q6-04 特許出願したものは全て特許庁で審査されるのではないのですか? A6-04 いいえ。特許出願しても審査請求をしなければ、特許庁で審査されません。 特許出願する出願人の意図には、本来の権利取得以外にも、競業他社が類似の技術を権利化できないように公開してしまうといった意図(防衛出願)や、現時点では発明の価値が不明なので取りあえず出願してしまおうといった意図等があります。したがって、審査請求率が高いということは権利取得を意図した出願が多いことを意味し、それゆえに、出願人がその技術を重視しているであろうとの推定が成り立ちます。 Q6-05 商品ラベルに特許番号ではなく特許出願番号を表記しているケースを見かけたのですが、特許出願番号の表記にどのような意義があるのでしょうか? A6-05 特許出願中のものであっても出願公開されれば、補償金請求権という一定の法的保護を受けることができます。したがって、法理論上は、補償金請求権を根拠とした他社牽制という効果があります。しかしながら、例えば電気・電子分野のように、特許が日常的に取り扱われるような分野では、特別な事情がない限り、その効果はあまり期待できないかもしれません。 |