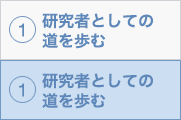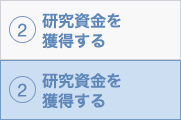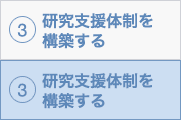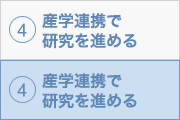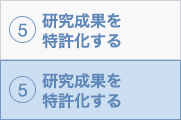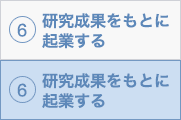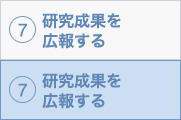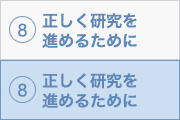リサーチ・アドミニストレーターが、研究を推進するための「触媒」になる
東京大学リサーチ・アドミニストレーター推進室 室長
松本 洋一郎氏

近年、大学教員とともに研究活動の企画・マネジメント、研究成果の活用促進等を行うリサーチ・アドミニストレーター(URA)の導入が進められている。URAの役割の本質とは、どのようなものだろうか。どんな人材が適任なのだろうか。東京大学でURAの導入を進めるリサーチ・アドミニストレーター推進室の室長を務める松本洋一郎氏にお話をうかがった。
・大学組織の人員構成と大学で行われる研究の質が変化したことから研究支援人材が必要になった。
・URAは、異なる組織を交わらせるための「串」になる。
・URAの仕事は、「研究者」のポテンシャルを活かすことである。
大学で推進する研究に、変化が起きた
 今から10~20年前、大学にも大きな金額の研究予算がつくようになったのが、URAが必要とされるようになった最初のきっかけだ。それまで「国プロ」と呼ばれる非常に大きな予算の研究プロジェクトは、国立の研究機関が中心になって運用してきていた。そのため、大学の組織体は、大きなプロジェクトのサポートに適したかたちではなかったのだ。しかも、2004年度の国立大学法人化の前後から事務職員の数は削減されていた。「大学組織としてのサポート体制が熟していればまた違ったのかもしれませんが、研究者には割と何でもできる人が多く、教員は研究とお金の両方のマネジメントを自分ひとりでやってしまったのです」。
今から10~20年前、大学にも大きな金額の研究予算がつくようになったのが、URAが必要とされるようになった最初のきっかけだ。それまで「国プロ」と呼ばれる非常に大きな予算の研究プロジェクトは、国立の研究機関が中心になって運用してきていた。そのため、大学の組織体は、大きなプロジェクトのサポートに適したかたちではなかったのだ。しかも、2004年度の国立大学法人化の前後から事務職員の数は削減されていた。「大学組織としてのサポート体制が熟していればまた違ったのかもしれませんが、研究者には割と何でもできる人が多く、教員は研究とお金の両方のマネジメントを自分ひとりでやってしまったのです」。
しかし、「何でもかんでも研究者がやるのは非効率」と松本氏は続ける。大きな研究費は、その予算元によって使い方が異なり、規制もさまざまある。それらを理解して運用しなければならないが、それをプロジェクトの代表研究者が行えば、本来であれば研究に割かれるべき頭脳を有効に活用できない。そんな状況を変えていこうという動きが、URAの導入につながった。つまり、研究を推進する上で必要なさまざまなことがらのうち「研究以外のすべて」がURAの業務範囲なのだ。
現場と本部、部局と部局をつなぐ「串」の役割
 東京大学では、呼称こそ「URA」ではなかったものの、これまでにも同じような役割を担う人材を雇用してきた。21世紀COEプログラムやJST戦略的創造研究推進事業のひとつERATOなど比較的大きな予算の研究プロジェクトにおいて、プロジェクトマネジメントを行ってきた「特任教授」がそれだ。
東京大学では、呼称こそ「URA」ではなかったものの、これまでにも同じような役割を担う人材を雇用してきた。21世紀COEプログラムやJST戦略的創造研究推進事業のひとつERATOなど比較的大きな予算の研究プロジェクトにおいて、プロジェクトマネジメントを行ってきた「特任教授」がそれだ。
その後、URA制度が動き出したところで国の補助金を活用し、本部が雇用したURAを、部局で推進している大型研究プロジェクトにそれぞれ配置した。東京大学のURAは、研究を進めている部局とともに、本部のリサーチ・アドミニストレーター推進室の両方の所属を持つ。普段は、研究が行われている現場である部局で仕事を遂行している。一方、本部では定期的にミーティングを設け、現場にはどんな仕事があるのか、どんなことが課題なのか等、現場で得た情報を共有し、ディスカッションを重ねる。「URAの組織をどのようにつくっていけばいいのか、URAが持つべきスキルは何だろうか、というようないわば『研究のマネジメント』を研究していたんですね。URAがこう働くことによって効率よく研究を推進できる、という知識を積み上げ、体系化してきました」。また、URAが各部局の「共通部分」となることで、組織の縦割りを廃する狙いもある。
研究者が「研究する能力」を発揮するために
 URAの業務内容は、研究費獲得のためのマネジメントや、プロジェクトにおける日々の費用管理、申請書作成、経理、法務、知財、広報など、非常に幅広い。それぞれの得意分野で棲み分け、仕事をするケースもあるだろう。
URAの業務内容は、研究費獲得のためのマネジメントや、プロジェクトにおける日々の費用管理、申請書作成、経理、法務、知財、広報など、非常に幅広い。それぞれの得意分野で棲み分け、仕事をするケースもあるだろう。
では、URAが共通して持っているべき資質とは何だろうか。松本氏は「研究は明日どうなるかわからないものであることを知っていること。想像力の豊かさが重要」と話す。「研究が計画通りに進むようにマネジメントする、なんて言葉を聞くことがありますが、淡々とやれば進むものには何のサプライズもない。それは日常業務であって、研究ではないでしょう」。研究のシナリオはフレキシブル。研究の進捗状況や結果に合わせてシナリオを最適に変化させていく力――研究者のポテンシャルを最大限活かすことがそのまま、研究の推進につながるのだ。
一方で、URAに最先端の研究をした経験は必須ではない、と言う。「たとえば、スポーツトレーナーは全員が元トップアスリートではないですよね。トレーナーの仕事は、アスリートの能力を最大限に引き出すことであり、そのためにはアスリートとは違うものが必要だと思うんです」。同様に、研究者とURAも、「研究を推進する」という同じ目標に異なる視点で向かうパートナーのような存在なのではないだろうか。松本氏も、「研究者はわがままだから、両方が研究者だとお互いの主張が絶対にぶつかりますしね」と笑う。
研究者の「仕事」は、学生の指導、大学や学会等の事務等、多岐にわたる。しかし、研究者の本質、研究者でなければできないことは「研究をすること」である、と松本氏。そのためには、考えごとをしたり、他の研究者や学生たちとディスカッションをしたりする時間が最優先だろう。「研究の先を見通せるのは、やっぱり研究者だけ。その研究者を活かしてなんぼ、と思える人がURAになるといいと思います」。URAは、研究環境を整え、研究者の研究者たる能力を最大限発揮させるための触媒になるのだ。
(取材・文 株式会社リバネス 2014年1月6日取材)
*コンテンツの内容は、あくまでも取材をうけた方のご意見です。