TOP
民間企業インタビューInterview
専門性を発揮しつつ、分野横断的な技術に取り組みたい人材に期待

互いに高め合える環境で
革新的な研究に携わり、成長する。
シンクサイト株式会社
執行役員 研究企画担当
杉本 慶樹 氏 博士(医学)
研究開発部 研究員
戸田 圭亮 氏 博士(工学)
研究開発部 研究員
河村 踊子 氏 博士(工学)
シンクサイト社は、光学・情報科学・バイオ工学などの先端技術を融合させることで、生命科学・ヘルスケアの発展と革新を目指すベンチャー企業。多様なバックグラウンドの人材が集い、専門分野の垣根を超えた研究開発に取り組んでいます。
執行役員の杉本氏は、「専門性を極めた経験は、他の分野を理解する上でも役に立つはず」と、博士人材への期待を語ります。研究員の河村氏、戸田氏を交え、ベンチャー企業におけるキャリア形成について語り合ってもらいました。
医療分野で
プラットフォームになり得る
革新的な技術
— まずは、会社概要についてご紹介ください。
杉本:当社は東京大学・大阪大学発のベンチャー企業です。東京大学と大阪大学の共同研究の成果として開発された「ゴーストサイトメトリー」と呼ばれる、新しい光学や機械学習の技術を使ってシングルセル(単一細胞)を形態によって分類可能な技術を事業化するために、2016年に設立されました。現在は約15名が在籍しています。

— 貴社の基盤となっている技術について、もう少し詳しくお聞かせいただけますか︖
河村:ゴーストサイトメトリーは、新規光イメージ圧縮測定法、機械学習を用いた新規多次元データ処理法、そしてマイクロ流体技術の融合によって実現した全く新しい細胞の分析分離技術です。これまで人が顕微鏡を見ながら行なってきた従来法に比べ、遥かに高速かつ正確に細胞を評価・選別することができる、革新的な技術です。この技術の研究成果については、昨年6月にScience誌に掲載されました。
杉本:特に医療や生命科学研究の分野においては、プラットフォームになる技術なのではないかと期待しています。例えば創薬事業においては、各大手製薬企業が年間数千億円という規模で研究・開発を行ってきましたが、ゴーストサイトメトリーを使うことで、創薬に必要な期間もコストも大幅に短縮することができる。また、細胞治療・再生医療分野では、効果が高く安全な細胞を素早く見分けられることから、より有効性が高く安全な治療につなげられる可能性がある。いわゆるゲームチェンジングな技術になり得ると考えています。
革新的な技術に惹かれて、
さまざまなキャリアを経た研究者が集う
— 皆さんはどのような経緯で入社されたのでしょうか︖
杉本:私は、もともと大手の製薬会社で創薬研究を行っていました。薬を生み出すには、先述のように多大な時間とコストがかかるという課題があります。また、製薬会社単体での開発は難しく、コア技術を持つベンチャー企業と共同開発することも視野に入れる必要があります。その製薬企業に在籍していた際には、様々な提携先候補を評価することも行っていました。そんなときに、シンクサイトとその技術のことを知ったのですが、これこそ創薬の課題を解決できる技術だと感じ、会社同士の提携ではなく、まず自分から飛び込んでみようと思ったのが入社の経緯ですね。
戸田:私は博士課程を修了したあと、理化学研究所で研究員として働いていました。バイオイメージング関係の研究をしていたのですが、技術開発をしてみたい気持ちもあり、このままアカデミアで研究を続けるか迷っていたタイミングで誘いを受けたのがきっかけです。キャリアチェンジを意識するようになってからは主にJREC-IN Portalを活用して情報収集していたのですが、当時の上司から紹介された当社のカルチャーや技術が魅力的で、就職を決めたという形です。
—河村さんは創業時からのメンバーなのですね。
河村:私は、出産で一度研究の現場を離れたあと、キャリアを再開するタイミングでJSPS(日本学術振興会)の海外特別研究員制度を活用してスタンフォード大学にポスドクとして所属していました。その後、子育てと仕事を両立させるため、帰国を検討していたところ、この技術の開発を始めようとしていた研究者が日本で技術補佐を探しているという話を聞き応募した形です。ですから創業以前からこの研究に関わってはいたのですが、創業後もしばらく子育てを優先し、技術補佐の業務を続けていました。子育てが少し落ち着いたタイミングで、当社に研究員として正式に入社したという流れになります。
— もともとの専門は今研究されているマイクロ流体工学ではなかったと伺いました。
河村:はい。大学院では物理情報やマテリアルサイエンスを専攻していました。細胞培養なども技術補佐の業務で初めて経験したほどです。医学部の先生に聞きながら勉強しましたね。
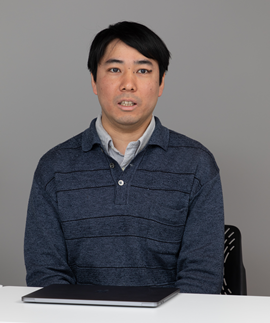

分野の垣根を超えて
高いレベルの研究に触れる経験が成長に繋がる


— 皆さん、ベンチャー企業で働くことに不安は感じなかったですか︖杉本さんは大企業からの転職ですが、比較してみてどう思われますか︖
杉本:ベンチャー企業の方が、経営が不安定だったり規模が小さかったりする分、リスクが大きいと言われることが多いですが、自分にとっては世の中の役に立つチャンスと捉えて入社したので、不安は全く感じませんでした。当社には私以外にも大きな企業から転職してきた社員が何人かいますが、ベンチャー企業で働くことをリスクと思っている人はいないと思います。逆に言うと、リスクと考える人はベンチャーやスタートアップでのキャリアは選択しないのではないでしょうか。
河村:私の場合は、もともと数名しかいなかったプロジェクトに、続々と優秀な人たちが加わり、今や15名を超える規模になった経過を見ています。不安というよりは、どんどん会社が大きくなっている感覚ですね。
— ベンチャー企業で働くことの不安よりもやりがいの方が大きいということですね。それでは、貴社で働く醍醐味を教えていただけますか︖
杉本:コア技術を持っているベンチャー企業全般に言えることだと思いますが、大企業と比べて、個々の研究レベルが圧倒的に高いので、互いに高め合える関係を築けます。また、光学、情報科学、バイオ工学など、さまざまなバックグラウンドの研究者が集まっている点も魅力だと思います。大企業と比べても圧倒的に多様性があります。以前勤めていた製薬会社で一緒に働いていた人たちは、基本的には似たようなバックグラウンドで、前提になる知識や用語はほとんど同じでしたから。
河村:この3人にしても全く専門分野が異なりますからね。杉本は生化学・細胞生物学、戸田は光学、私はマイクロ流体工学。更に社内には、機械学習やソフトウェア開発、機械・光学設計を専門にする人材も在籍しています。それぞれチームで動いていますが、人数が少ない分、期待も責任も大きい。自分がそこにいる意味を実感できるのは大きな醍醐味だと思います。それから、論文を積極的に学術誌に発表して技術をアピールする社風。実際に私も昨年、著者の一人としてScienceに論文を発表しました。アカデミアにいなくても論文が書けるという点は、他の会社とは違う魅力なのではないでしょうか。
ひとつの分野を極めれば、
そこで得た経験を応用できる
— ベンチャー企業にはどんな人が向いていると思いますか︖
戸田:環境も研究も変化が早いので、地道にひとつのことを極めるタイプよりも、変化の流れに乗ることを楽しめる人の方が向いていると思います。
河村:専門領域を超えていろいろなことをしなければいけないですからね。それぞれの専門分野を融合してひとつのシステムをつくるので、専門性を持ちつつ、すべてのジャンルをある程度理解できることが求められますね。
戸田:私は前職の理研でも当社と同じように他分野の人たちと一緒に働く環境でしたので、それが通常の感覚ですね。わからないことがあれば聞く、ということが当たり前にできることが大切なのではないでしょうか。


— 人によってはその当たり前のことが難しい場合もありそうですね。皆さんはどのように適応されているのでしょうか︖
杉本:私がいつも感じているのは、まずひとつの分野で確固たるものを築くこと。その過程で得た経験は他の分野にも応用できると思うんです。自分の核を明確にして、軸足をそこに置いたうえで一歩を踏み出すことが大切だと思いますね。
戸田:そうですね。プロフェッショナルな部分がひとつあれば、周辺の知識を補完するだけで他のことにも応用が利きますから。その能力は、他分野の人と積極的に交流することで身につくものだと思います。
—採用についてお聞きしたいのですが、貴社ではどのような人材を求めているのか、また、ベンチャー企業を志望する求職者は、どのようなアピールするとよいのかを教えてください。
杉本:当社の場合、創業当初の研究フェーズでは、新しい技術をつくれる能力を持った人材が求められてきたと思いますが、今後はつくり上げた技術が医療や生命科学分野を変革できるのかを実証し、世の中に届けるフェーズに移ってきています。新しい技術のポテンシャルを最大限引き出せるような柔軟な発想と、世の中に届けるための実行力、開発力が必要です。また、解決しようとしている社会課題やお客さまのニーズを汲み取って改良していく能力が求められると思います。プロフィール等に関しては、自分のやってきたことを簡潔に記載してほしいですね。自分の研究について、分野の異なる人にも理解しやすいように説明できる能力があるとわかれば、私たちも声をかけやすくなると思います。
— 企業での実務経験は重視されますか︖
杉本:そうとは限らないです。アカデミアでキャリアを積んだ方は研究の核をしっかり持っていますから。無理をしてビジネス寄りのアピールをしなくても、自分ができることを正直に書いてもらった方が、お互いにとっていい結果に繋がると思います。
各々が研鑽を積み、技術の実用化に力を尽くす
—今後、ご自身がどのようなキャリアを築いていきたいか、または会社をどのように成長させていきたいか、それぞれお聞かせいただけますか︖
戸田:この会社でいろいろな分野の人たちと関わっていると、自分の知識が足りないことを実感する機会も多くなります。他分野の知識をもっと取り入れて、技術の全てを把握している状態になりたいというのが当面の目標です。長いスパンの目標としては、蓄積した知識やノウハウをもとに、会社を大きくするための施策に関わっていけるようになりたいですね。
河村:個人としては、今のパフォーマンスを上げるためにやらなければいけないことを考えて、実行していくことですね。会社に関しては、持っている技術がひとつのプロダクトとなって、研究者や医療の現場の皆さんに使ってもらうことが目標です。働き方についても考えていきたいですね。これからも、海外の方や女性を含めて、多様な人が働きやすい会社であってほしいと思います。
杉本:私たちの技術を、医療や生命科学研究に関わるプラットフォームにどれだけ早く近づけるかを考えていきたいですね。それが実現できれば、自然と世の中の皆さんに認知してもらえる会社になっていくと確信しています。
— ありがとうございました!
